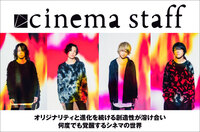Japanese
2018年04月号掲載
brainchild's × cinema staff
brainchild's:菊地 英昭(Gt/Vo)
cinema staff:飯田 瑞規(Vo/Gt)
インタビュアー:TAISHI IWAMI Photo by 石崎祥子
-THE YELLOW MONKEYの魅力はまさにそこだと思うんです。色褪せることなく、世代継承されてる。2004年に解散されて、2016年に再結成されるまでの間に、THE YELLOW MONKEYを知って復活ライヴに行った人も、たくさんいると思うんです。
菊地:"同じ年齢層の人や30代、40代の人が多いのかな"って思ってたんですけど、若い人もたくさんいて。THE YELLOW MONKEYを好きになったものの、もう解散していたからライヴを観られなかった若い人がたくさん来てくれたのは、本当に嬉しかったです。
飯田:僕もそうですから。復活の発表があったとき、すぐに同世代の友達とやりとりしましたもん。
-菊地さんの世代は、ちょうどお生まれになられたころに、THE BEATLESやTHE ROLLING STONESといったビート・バンドがヒットして、そこからサイケデリックへと流れていった時期。さらにプログレッシヴ・ロックやハード・ロックが生まれて、1970年代後半になるとパンクが出てくる。
菊地:大きく言えばそんな感じですよね。
-そういった現代ロック創成期からの文脈をレコードや本とともに追って体験された方と、飯田さんのように1990年代のオルタナティヴ・ロック以降の生まれで、情報の取り方もデジタルが主流になってくる世代間が、どんな音楽の話を交わすのか。とても興味深いです。
飯田:僕は1990年代のオルタナティヴ・ロックから入って、好きなバンドが影響された音楽を掘り下げていったんですけど、周りの人も含めて、そこまでしっかり掘れている人となると、そんなにいない。菊地さんが初めて買ったとおっしゃったQUEENのようなスタジアム・ロックも、一応聴いてはいるんです。でも、ちょっと想像がしづらいというか、存在としてあまりにかけ離れてる感じがして。というのも、自分が最も多感だった高校生くらいのとき――2000年代って、スター的なバンドが出てきてないんですよね。RADIOHEADも少し前だし、ARCTIC MONKEYSとかもいますけど、全体的にあのころの感覚とはまた違う気がしていて。
菊地:今の若手となると、スタジアム・バンドっていう感じの、海外でもいないよね。どこで切れたんだろう?
-QUEENのFreddie Mercury(Vo)とBrian May(Gt)のように、フロントマンやプレイヤーが個として世界中で認識されている、となると特に少ないのかもしれません。ここまでで挙がったバンドくらの規模感で、となると、それこそARCTIC MONKEYSのAlex Turner(Vo/Gt)とかそのあたり、2000年代中期に出てきたバンドで切れてるんじゃないかと。
飯田:たしかにそうかもしれません。バンドというか、バンドの中の個人として、絶対的な存在として認知されている"ロック・スター"、みたいな人が少ないのかもしれませんね。
-THE YELLOW MONKEYは吉井和哉(Vo/Gt)さんという絶対的なフロントマンがいて、全員の絵が浮かびます。
菊地:だと嬉しいです。
飯田:そうですよね。復活してくれて本当に嬉しいです。
-THE YELLOW MONKEYが再結成できた理由を教えていただけますか?
 菊地:すでに違うバンドを経験してた人間が集まったバンドで、"微妙な距離感"をちゃんと保ってたから、再結成できたのかもしれません。完璧にべったりで喧嘩とかしちゃうと、もうアウトだったと思います。
菊地:すでに違うバンドを経験してた人間が集まったバンドで、"微妙な距離感"をちゃんと保ってたから、再結成できたのかもしれません。完璧にべったりで喧嘩とかしちゃうと、もうアウトだったと思います。
飯田:『THE YELLOW MONKEY LIVE AT TOKYO DOME』(2004年リリースのライヴDVD)を観ていて思ったんですけど、あのライヴは結成されてから12~3年くらいですよね? 僕ら(のバンド)が今のメンバーになってからの年数に近いんですけど、バンドがどんどん自分たちのものじゃないぐらい大きくなっていく感覚って、どういうものだったんですか?
菊地:自分たちは絶対にそこまでやれると思ってたから、突き進んでた。時代も時代で、ライヴをやれば人が入るし、CDもよく売れたし。そこでスタッフや周りの関わってくれる人も含め、どんどん大きくなっていって。そうすると、自分たちで発信してやってる感覚がないのに、なんかとてつもないことが動いてる、そんな怖さもあったような。
飯田:なんて貴重な話を......。
菊地:そうなってくると、別に仲が悪いわけではないんだけど、他のメンバーのことを気にかけられなくなってくるんだよね。誰かが音楽的なことで悩んでいたとしても、気がつかない。そうしてバラバラになってきて、当然音に及ぼす影響も大きくなってきて。それが、解散したもっとも大きな原因なんじゃないかと、振り返るとそう思う。何かひとつ決定的なことが起きたというよりは、あの波のデカさに、結局自分たちは飲まれたのかもしれないね。cinema staffはそのへんどうなの?
飯田:僕らはじっくり地道に、ここまでやれてることをありがたく思ってます。
菊地:うん、そうやって続けられることも、なかなかないからね。
飯田:菊地さんは"じっくり続けていきたい"みたいな、感覚はなかったんですか?
菊地:デビューしたときに、事務所の社長やレコード会社の人に、"君たちは渋公(※渋谷公会堂/2015年に閉館)くらいの規模で、ずっと末長くやっていけるバンドを目指すのか、チャートで1位を取って、アリーナや武道館でやるようなアーティストになるのか、どっちだ"って聞かれて、後者だって言ったんだよね。前者も自分の夢ではあったけど。だから前だけしか見てないし、そこで盲目的になってたのかもしれない。で、解散したあとに気がついたのは、渋公ぐらいでコンスタントでやれることこそが、ひとつの確固たる世界。だから、それでいいんだって。そこが土台にあって、さらに大きくなるのかならないのかって話。
RELEASE INFO
- 2026.03.10
- 2026.03.11
- 2026.03.13
- 2026.03.14
- 2026.03.17
- 2026.03.18
- 2026.03.20
- 2026.03.21
- 2026.03.23
- 2026.03.24
- 2026.03.25
- 2026.03.27
- 2026.04.01
- 2026.04.03
- 2026.04.06
- 2026.04.08
FREE MAGAZINE

-
Skream! 2026年02月号
Cover Artists
Mori Calliope