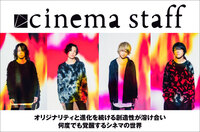Japanese
2019年09月号掲載
cinema staff
Member:飯田 瑞規(Vo/Gt) 辻 友貴(Gt) 三島 想平(Ba) 久野 洋平(Dr) 高橋 國光
Interviewer:沖 さやこ
-國光さんはいかがですか? the cabsの頃からずっと、ブログなどでもよくcinema staffのことを褒めていましたが。
高橋:僕は三島に対して尊敬の念が強いんですよ。"こんなにいい曲ばっかり作るやつおるんか"ってずっと思ってた。昔の俺は三島想平になりたかったんです。俺にないものをこの人は持っている。こいつに比べてなんて俺はだめなんだろう! という気持ちでいた。三島が言っていた通り、それこそ10代、20代のときなんかでは悔しさが爆発しちゃって共同制作なんてできなかったです(笑)。出会ってから10年経って、やっぱり俺は三島にはなんにも勝ててない。でも、それを通り越して、自分もちょっと丸くなったなと感じるんで、"三島だったらもっと良くしてくれるな、三島に渡せば間違いないでしょ"と思いました。楽しいだけでやれましたね。
-10年という時間がそうさせてくれたんですね。
飯田:そうですね。まさに。
三島:大人になるとこういう感じになるんだなー......と思いますよね(笑)。
-ははは(笑)。30代は人生の伏線回収みたいな出来事が怒濤のように訪れますから。
三島:「斜陽」の制作もそういう感じはありましたね。ぶっちゃけ、久野に提案されたときは"マジか~。やれるかなこれ!?"ってめっちゃ不安だったんですよ(笑)。
久野:なんならちょっと反対されました(笑)。三島としては自分の作ったまっさらな2曲の新曲でいきたい気持ちもあったと思うし、いろんな気持ちがあるのはわかってたけど......。國光とライヴをする必然性を生むのは今しかない! というところをごり押しして(笑)。
-久野さんの思いつきやごり押しで物事が動き出すのは、cinema staffあるあるですからね。
三島:半分......いや、8割くらい久野が動かしてますね(笑)。
久野:たしかに"あ、面白い!"と思っちゃったら、ひたすらその良さを説明してごり押してるかも(笑)。今回も想像したときにすげぇわくわくしたから。ベスト・アルバムを出せるほど活動できたことは嬉しくもあるんですけど、やっぱり過去に出した曲ばかり入っているCDをお客さんに買ってもらうことは、あんまり気持ち良くできることではなくて。だから、自分たちの中のベスト・アルバムのイメージを変えたい気持ちもあった。面白いことをしたい......と考えたら、國光との共同制作は絶対にわくわくできたんです。結果的に、ベスト・アルバムを作ってみて良かったなって。
-そうですね。「新世界」という新曲でメジャー時代のリード曲を網羅したDISC-1の幕を開けて、"インディーズ"時代の楽曲で構成されたDISC-2の最後に「斜陽」が入ることで、歴史のひとつの着地点という意味が生まれています。國光さんが少しずつ音楽活動を続けているなかで、二十歳前後の頃から親交のあるバンドと共同制作をすることで、さらに表舞台に立つというのも、感慨深いものがありますし。
久野:the cabsは俺らが東京で初めてできた友達だったし、プリプロを送り合ったりもしてたくらい仲も良かったけど、the cabsのファンでもあったので、國光が表舞台に戻ってきてくれるのはすごく嬉しいことでした。じわじわこっち側に来てくれました(笑)。
高橋:俺はcinema staffのただのファンですから。ただのファンだし、それでいいと思ってた。追っているだけでいい、ただただシンプルに大好きなんです。だから今回一緒にやれて、嬉しかったし楽しかったですね。
-ギタリストである國光さんがソングライティングに参加しているとなると、ギタリストである辻さんの心情も気になりますが。
辻:國光のギターはすごく好きだし、ずっと嫉妬してた。自分がイメージする、弾きたいギターを國光はずっとthe cabsで弾いてたんです。僕はどこに持っていったらいいんだろうと悩んでた時期もあったし。the cabsが解散したあと、"cinema staffの曲で國光みたいなギター・フレーズ弾こう"と思った時期もあったし(笑)。
高橋:俺は今も昔も辻さんともっと仲良くなりたいと思ってますよ!?
辻:もうそういうのはないから安心して(笑)! 「斜陽」の制作も"ギターをこういうふうにつけます"と返したら、"じゃあこうします"とフレーズが変わって、"じゃあ僕もこうします"みたいなやりとりができたから、すごく楽しかったです。レコーディングまでずっとフレーズが固まってない感じも、その場の力でやった感じがあったので、良かったですね。
久野:そういうレコーディング・マジック、今回結構あったよね。"お、そうくるんや!"みたいなのの連続で面白かったです。
-レコーディングの様子もInstagramのストーリーズで見てましたけど、みなさん楽しいが溢れまくってましたもんね。
高橋:人生で一番楽しい瞬間でした。トータル30年生きてきて、プライベートを含めても1位だった(笑)! ......10代の頃から、自分なんかが音楽をやっていることがずっと後ろめたかったんです。その後ろめたさを感じないで過ごせたのは初めてだったので、楽しいという気持ちで音楽をやってもいいんだなって、どんどん攻めていきました。"いっぱい音入ってたほうがかっこいいんじゃね?"とか言って。
久野:盛る方向だったね(笑)。そういうところに懐かしさも感じつつ、今までやってきたことがあるからこそできる感覚もあったのが良かったですね。全員に余裕が生まれてた。
飯田:三島が國光に電話をしてから曲ができていくスピード感が尋常じゃなかったんです。だから高いテンションのままレコーディングまで突っ走れた感覚があって、レコーディング中も"これきてるぞ! 絶対いいものができるじゃん!"と感じてて。エンジニアさんも、the cabsもcinema staffも録ってくれてた人たちだったので、そのおふたりのテンションもすごく伝わってきました。いいものができないわけないなってみんながみんな感じてたと思います。
-2010年代初頭は全国デビューをして勢いを増すthe cabsがいて、その同世代にcinema staff、tricot、plenty、indigo la End、きのこ帝国、THE NOVEMBERSがいて。オルタナ/ポスト・ロック/エモ/シューゲイザーが土台にある若いギター・ロック・バンドの文化ができていて、それが大きくなっていたと思うんです。でもthe cabsが解散したことで、世間の潮流は違う方向に行った。だから、"the cabsが解散してなかったら音楽シーンはまた違ったのかもしれないな"と思うこともあって。
久野:たしかに、the cabsが解散したことで流れは変わりましたよね。僕らもその潮流の変化の煽りは確実に受けていて。正直、「斜陽」も変な曲だと思うんですよ。こんな5拍子の曲をやってるバンド、いろんなフェスを観ていてもなかなかいないし。でもそれを気にせず、強い気持ちで演奏できる感じにはなってきたかな。だから、今回國光が表舞台に戻ってくることによって、新しい流れが生まれないかなというのはちょっと期待しているところでもあるんです。
-そうですね。「斜陽」を聴いていて、あの文化はブームにならなくて良かったのかもしれないと思いました。あのままthe cabsが続いていたらこの2組は共同制作もしていなかったのかもしれないですし。
飯田:あのときの國光の選択は、すごくわかるんです。"なんで全部放り出して行っちゃうの!?"とは言えなかった。俺がその選択をする可能性だって全然あったから。
久野:うん。みんなそうだったよね。國光の選択を咎める人はあんまりいなかった。だから、國光がああいう行動に出たときは、どこかでみんな"あぁ、だよね"と思ったというか。ただ、せっかくのいいバンドがなくなってしまったことが悔しいという。
RELEASE INFO
- 2026.03.10
- 2026.03.11
- 2026.03.13
- 2026.03.14
- 2026.03.17
- 2026.03.18
- 2026.03.20
- 2026.03.21
- 2026.03.23
- 2026.03.24
- 2026.03.25
- 2026.03.27
- 2026.04.01
- 2026.04.03
- 2026.04.06
- 2026.04.08
FREE MAGAZINE

-
Skream! 2026年02月号
Cover Artists
Mori Calliope