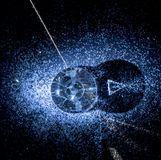Japanese
2022年07月号掲載
ヒトリエ
Member:シノダ(Vo/Gt) イガラシ(Ba) ゆーまお(Dr)
Interviewer:秦 理絵
ロックって暴力的だったり、速くて強い、みたいなものが根底にあるけど――聴き手側がそこに優しさとか美しさを感じてるだけなんです
-聴き手を選ばずに届きそうな曲というと、シティ・ポップっぽい「strawberry」なんかは、例えば、「みんなのうた」で流れていそうな耳に残る歌ですよね。
シノダ:うん。「みんなのうた」っていうのが今回のテーマかもしれないです。そういう意味で、「strawberry」と「ゲノゲノゲ」は同列なんですよ。
-曲調は全然違うのに?
シノダ:要は、どうやったら聴いてもらえるか? というのを考えたときに、1回聴いたら忘れられないメロディを作るしかないんだって、そこに行き着いたんですね。「curved edge」(2020年リリースのデジタル・シングル)とか「ハイゲイン」(『REAMP』収録曲)とか「3分29秒」では手ぬるかったところ、まだ到達しなかったところに対して、これならどうだ! って作ったのが「ゲノゲノゲ」だったんです。
-メロディの中毒性がすごい曲です。
シノダ:ここまでやったら文句ないだろうっていうぐらい、とにかく覚えやすい音楽を作ったんですよ。「strawberry」はその余波で生まれた感じですね。A、B、サビっていう概念じゃなくて、トータルとして覚えてもらいたいなと思って。
-一般的な曲であれば、まずサビが一番インパクトに残るけれど、そうじゃない。
シノダ:そもそもA、B、サビの概念がない曲のほうが歌謡曲として正しいと思うんです。童謡にA、B、サビとかないじゃないですか。それぐらいの曲を作りたかった。「ゲノゲノゲ」はsyrup16gの「Reborn」みたいなイメージです。あれって、どこがAだかBだかわからない名曲じゃないですか。そういうものを目指したいなって。
イガラシ:曲を作ってるときは、シノダがメロディに対してそこまで向き合ってるとは思ってなかったんですけど、特に「ゲノゲノゲ」とかは、何がキャッチーか? って考えてるんだろうなというのは受け取ってました。そういう曲なのに、逆に1コードで押し切ってるところが、僕は歪で好きなんです。
-たしかに「ゲノゲノゲ」も、「strawberry」も、メロディを際立たせた曲にしようと思うと、オケがシンプルになりがちなんだけど、そうじゃないのが面白いですよね。
シノダ:もっと音楽を聴けっていう気持ちが強くなってるかもしれないです。そのために最後まで聴かせる工夫が必要だったんですよ。僕は、音楽はこうじゃなくちゃいけなくて、みたいな風説を本当に憎んでるので。「ゲノゲノゲ」はこれでもかって言うぐらいギターを目立たせてやったし、「strawberry」はこれでもかっていうぐらい汚いギター・ソロを入れてやりました。苛立ちのベクトルをそういう方向にぶつけてるんですよね。
ゆーまお:「ゲノゲノゲ」の途中のソロとかも最初のデモから入ってたしね。
イガラシ:あそこはベースを弾く感覚からすると、不自然なことを急に差し込んでるんですよ。サンプリングっぽい掛け合いになってて。ああいうのはシノダのアイディアですね。
ゆーまお:あと、最近のシノダはスネアにバック・ビートさせない曲が多いんですよ。他の音で補ってるから聴くぶんには違和感はないと思うんですけど、バンドをやってて、そういう経験はあんまりないので。「ゲノゲノゲ」もそういう曲です。
-ちなみに「strawberry」は別れの曲として書いたんですか? "ぼんやりとしていたら/はなればなれになってしまうよ/白い靴下みたいに"は詞的で素敵でした。
シノダ:いや、別れの歌のつもりではないですね。うだうだ、だらだらと暮らしている人たち、みたいなものかな。そういうやつらって自然とバラバラになってしまうんですよ。でも、この先のことを考えずにずっとだらだらと過ごしてる美しさ、楽しさもあるよなっていうことを考えながら作った曲でした。そういうのはいつか終わるけどねって。
-最後にアルバムを締めくくる「Quit.」について聞かせてください。イガラシさんが作曲を手がけた曲って、切なくて泣きたくなる曲調が多いんですよね。
シノダ:これはだいぶ泣かせるように作ったからね(笑)。
イガラシ:この曲は過渡期にいるような心境をイメージしてたんです。季節とか時間とか、何かが終わるときは、当然悲しかったり寂しかったりすると思うんですね。でも、それまでに経験したことが大好きだったら、それに対する感謝とか優しい気持ちも含まれてると考えてるんですよ。そういう複雑な感情がメロディになったらいいなと。
-それは歌詞を書くシノダさんには伝えたんですか?
イガラシ:伝えません。
シノダ:何も言われてないですね(笑)。
-でも、歌詞にちゃんと落とし込まれてますよね。
イガラシ:そう、だからびっくりしたんですよ。歌詞に"それでも君の夏が来る"って歌ってるけど、僕も夏の終わりをイメージして作ってましたから。
シノダ:こういう歌詞を書けば、イガラシが喜ぶのはわかってるのでね(笑)。何かに魅せられて、謎のスピード感に駆られて生きていく人たちって美しいよねと言ってあげたかったんですよ。それがロック・ミュージックのやることだと思うんです。僕はそういうふうに物事に対する情熱がピークみたいになる瞬間を夏って呼ぶんですよ。それが私にはもう来ないけれど、あなたには来るよっていうことを言いたかった曲です。
-なるほど。
イガラシ:あと、たまたまこの曲を録るタイミングで、FOO FIGHTERSのTaylor Hawkins(Dr)が亡くなったんですよね。彼が残してくれたものに対する愛情とか感謝みたいなものが、この曲でやりたかったことと一致してるなっていうのもあって。ゆーまおもTaylorのドラムが大好きなんですね。だから、ちょっと思い切ってTaylorをイメージしてぶっ叩いてくれない? みたいなことを言ったんです。
ゆーまお:うん、言われた。海外のロックって日本じゃ考えられないぐらいドラムの音がデカいんですよ。Taylorはそれの代名詞みたいなスーパー・ドラマーなので、あんなの真似するなんて絶対にできない。それはわかったうえで思いっきりやってみたんです。そしたら、どんなに思いっきり叩いても、ガチャガチャした音にならなかったんですよね。
イガラシ:ゆーまおはきれいに鳴らしちゃうから。
ゆーまお:ただ、ロックってそうだよねって思ったんですよ。暴力的だったり、速くて強い、みたいなものが根底にあるけど、聴き手側がそこに優しさとか美しさを感じてるだけなんです。そういう音像の仕上がりを見せたいなと思いましたね。そういう意味で非常にロックなドラムにはできたなって実感がある曲です。
-わかります。最初に"今回は優しいアルバムだと思った"と言いましたけど、それは最後の「Quit.」が持ってる神聖な包容力みたいなものの余韻も大きいんだと思います。
シノダ:たしかに。スタジアムが似合う曲にもなりましたね。
-アルバムのタイトルを"PHARMACY"にしたのは?
シノダ:まず語呂が良かったんですよ。意味は調剤薬局です。年始の話なんですけど、本当に精神状態が良くなかったんですね。ライヴでははっちゃけてましたけど、正直バンドマンとしてのバイタリティが下がってて。そこに不安を感じてたんです。でも、今回のアルバムを作っていくうちに回復したんですよ。その状態まで僕を導いてくれたアルバムっていう意味を込めての"PHARMACY"。なので、完全に僕の主観ですね。
-聴き手にもそういう役割を果たすアルバムになってほしいという願いはありますか?
シノダ:そうなればいいなぁっていうぐらいですかね。
-今回のアルバムにはバンドとして新しいチャレンジがたくさんあるけど、いつも人の孤独に寄り添ってきたヒトリエの在り方は変わっていない。そういう意味で、"PHARMACY"というタイトルはぴったりだなと思いました。
シノダ:そう受け取ってもらえると嬉しいです。わりとバンドってみんなそんなもんなんじゃないかなとも思うんですよ。これは人の言葉を借りますけど、ライヴっていうのは、音楽をやる人たちにとっても、聴く人たちにとっても、セラピーである。そういう表現があるように、音楽に癒しの側面があるのは僕らに限った話ではないと思うので。『PHARMACY』が特効薬ですよって言うのは驕りに近いというか、恐れ多い。
-だから、これは完全に自分にとっての主観のタイトルだと言ったんですね。
シノダ:そういうことです。
RELEASE INFO
- 2026.03.04
- 2026.03.06
- 2026.03.10
- 2026.03.11
- 2026.03.13
- 2026.03.17
- 2026.03.18
- 2026.03.20
- 2026.03.21
- 2026.03.24
- 2026.03.25
- 2026.03.27
- 2026.04.01
- 2026.04.03
- 2026.04.08
- 2026.04.10
FREE MAGAZINE

-
Skream! 2026年02月号
Cover Artists
Mori Calliope









![オン・ザ・フロントライン / センスレス・ワンダー[ReREC]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WsScYhcCL._SL500_.jpg)