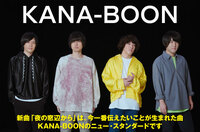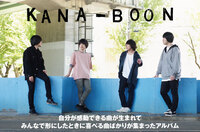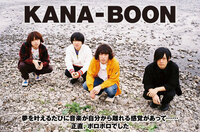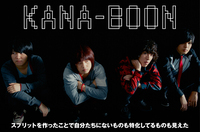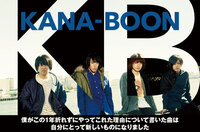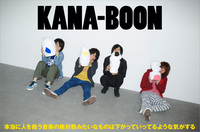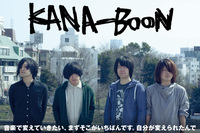Japanese
2016年01月号掲載
KANA-BOON
Member:谷口 鮪(Vo/Gt) 古賀 隼斗(Gt/Cho) 飯田 祐馬(Ba/Cho) 小泉 貴裕(Dr)
Interviewer:石角 友香
-そういう状況って、KANA-BOONみたいにポピュラリティのある場所でやってるバンドにとっては歓迎すべきことなのかな?と。
古賀:どっちとも言える。今は僕、すごく賛成の方なんです。僕らが今やってるこういうバンドの形というか、ちゃんとベース、ギター、ドラム、ヴォーカルで"俺らでやろうぜ"って組んだバンドがテレビに出るとすごく嬉しいんです。でも、テレビに出るようなバンドはみんなそういう認識をちゃんと持って欲しいというか。テレビに映し出されたものが真実として捉えられることが多いので、だからそういう場でバンド感を損なったようなバンドがあんまり出て欲しくはないとは思っています......あかんかな?
谷口:物申したなと思って。
古賀:そう? バンドらしいバンドがテレビに出てるのは今はすごく嬉しい。バンドらしくない人たちがテレビ出て、それがバンドやと思われるのは俺はすごくイヤ。
谷口:やっぱ理想としては――僕らはテレビに出て、それを次に繋げたいって気持ちでいつも出てるんですよ。それこそライヴに来て欲しいとかね。それでKANA-BOONのことを知って好きになって、実際ライヴに来たり音楽を聴いたりして、そこで改めてちゃんと出会ってくれたら1番嬉しくて。でも理想としてはテレビで流れた瞬間に何かが伝われば1番いいんですけど。
-それもバンドの強さでもありますし。さて、肝心のシングルですが、前作以降のシングルってKANA-BOONなりに大人っぽいことをやってると思うんですけど、今回が1番、一見シンプルで難しいことをやってるんじゃないかと。
谷口:はい。
-極端に言うとメロディック・パンク的なニュアンスも感じて。今までやってなかったことなんじゃないかと思うんですが、どういう発端を持った曲なんですか?
谷口:できたのは5月ぐらいで。だからアルバムめがけては作ってなくて、別のシングルの候補として作ってあった曲なんです。アルバムの話が出てからもアルバムに入れる気配はなかったんですよ。でも、それから先行シングルを切るってなったとき、この曲とかがいいんじゃないかって話になって。
古賀:「ランアンドラン」はアルバムの聴かせたいところというか、メッセージ性みたいなところを担う曲やったんで、そういうものが導かれるシングルにしたいなっていうので、今回のシングルはこの選曲になりました。
-歌詞もストレートだなと思いました。
谷口:そうですね、まぁ曲がシンプルやしまっすぐやから、ちゃんとまっすぐな言葉を乗せんと意味がないと思って書きました。
-ここ1年ぐらいのアレンジで言うと、古賀さんのギターのアレンジが印象的でしたね。
古賀:今回、Bメロの3音がヴォーカルとユニゾンしたり、サビの頭の入りやったり、後半の譜割りがサビとユニゾンやったりするんです。そういう意味でシンプルに聴こえたりもするんですけど、歌メロがすごく良かったっていうのが最初にあって。プリプロのみんなで合わせてる段階では、Bメロとサビだけあったんですけど、その時点で絶対この歌メロは響くと思ったのでそれを補強する形でギターを重ねていきましたね。
-わかりやすい展開といくつかの山を作ってというより、もっと立体的になっていってるように最近の曲は感じます。
古賀:(笑)なんか冷静に聴けるようになったのが1番でかいんかなと思いますね。その、他人の曲として客観的に聴けるというか。そのへんをちゃんとできるようになってきたのかなと思いますね。
-この曲はメッセージが核にあるということでしたが、どうとでも受け取れる歌詞じゃないですか。
谷口:"そうでありたい"っていうのは思っていますね。でも最初書いたときはあんま良くない歌詞になってもうてて。間口を広くしようって意識がすごくあって、誰が聴いても響く曲を作りたいって気持ちやったから、誰にでも当てはまりすぎて中身がない歌詞になってしまって。そこから書き直してでき上がったのがこれなんですけど、メインとしては若い子たちに刺さる曲でありたいなという狙いがあって。ほんとにこれからの卒業とか今までずっと馴染んできた環境から、またゼロからの道を進んでいく子たちに聴いて欲しいなって気持ちですね。だからもう卒業式の前日みたいなことを......想像しながら。まぁそれに僕らとしては、このタイトルの通り、"走って、そして走って"みたいな時間をずっと過ごしてきたから、これが自分たちのやり方やって表明する意味合いがあって。それに最後のサビの締めの一節はほんとに、その物語の登場人物の気持ちであると同時に僕らの純粋な気持ちでもあるんです。僕らはどこまで行っても大事な人は絶対に置き去りにはしないっていう気持ちでやってるし、それをちゃんと今、僕らを見てる人にも伝えたかったんです。そういう思いがあってでき上がった歌詞です。
-活動自体は続いてるんだけど、ある種見えない節目を作ろうとしてるのかな?っていうふうにも聴こえたんです。
谷口:うん。その通りです。
RELEASE INFO
- 2026.03.13
- 2026.03.14
- 2026.03.17
- 2026.03.18
- 2026.03.20
- 2026.03.21
- 2026.03.23
- 2026.03.24
- 2026.03.25
- 2026.03.27
- 2026.04.01
- 2026.04.02
- 2026.04.03
- 2026.04.06
- 2026.04.08
- 2026.04.10
FREE MAGAZINE

-
Skream! 2026年02月号
Cover Artists
Mori Calliope