DISC REVIEW
-

-
YĪN YĪN
Yatta!
"Yatta!"はこっちのセリフだ。何せ、Martin Dennyから伝来し、YMOとして結実したエキゾチカが、時代と国境を越えオランダの地で花開いているのだから。このロマンには"Yatta!"と言わざるを得ないものがある。さて、東洋の匂いやレトロな質感といったマニアック且つあけすけな作為が2026年の作品として成立しているのは、作品の骨子であるそのグルーヴの精密さゆえ。前作と比してファンクの成分はやや減退し、特に後半にかけて粘性の高い"聴かせる"展開が主張する本作は、YĪN YĪNのクレヴァーさを知るには絶好の一枚だろう。ロック・リスナー諸氏においても、ぜひこの曲芸めいたサウンドの奥に光るクラフトマンシップの冴えに触れてほしい。(藤村 太智)
-

-
DRY CLEANING
Secret Love
英ロンドンの4人組ポストパンク・バンド DRY CLEANINGの3rdアルバム『Secret Love』が名門レーベル 4ADよりリリース。本作の聴きどころは、緻密に設計された音の抜き差しや巧みな残響音のコントロールで表現される流麗なサウンドの変化だろう。特にTrack.7「Evil Evil Idiot」のサウンド・デザインはアルバムの中でも白眉の出来と言ってよく、ノイズと残響音が立体的に絡み合う複雑なテクスチャーにどっぷりと浸ることができる。また、これまでの彼等の作品と比べて有機的でダンサブルになったリズムが楽曲を下支えしており、バンドの肉体的な進化も感じられた。ぜひ静かな場所で一つ一つの音の移り変わりを楽しみながら聴いてほしい一枚。(水田 竜介)
-
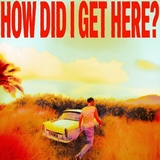
-
Louis Tomlinson
How Did I Get Here?
史上最も売れたボーイズ・グループの1つ、ONE DIRECTIONの活動休止から10年、シンガー・ソングライターとして活躍しているLouis Tomlinsonがソロ3rdアルバムをリリース。ノスタルジックな手触りの、ポップスでもあり、インディー・ロックでもある絶妙なポジションでリスナーを惹き付ける彼の音楽は、UKサウンド好きにはたまらないツボを押さえている。温かみがあって、きれいに作り込みすぎていないところもいい。男性アイドルも飽和状態な昨今の音楽業界を見ると、彼のように自身の音楽的才能1本で生き残っていけるシンガーってどれだけいるんだろう? と思ってしまう。それだけ、1Dというか、Louis Tomlinsonが偉大であるということなんだけれども。(山本 真由)
-

-
SECOND HARBOUR
Coalesce
カナダの3ピース・エモーショナル・ロック・バンド SECOND HARBOURが、SharpTone Recordsと契約してデビューEPをリリース。アルバム・リリースはまだだけれど、ぽつぽつと発表してきた楽曲のクオリティの高さで、その実力が認められた形だ。まずは、その感情を揺さぶるメロディの切なさと、なんとなく日本のインディー・ロック好きにも刺さりそうなギター、ハードに打ち込むドラム、あとはとにかくヴォーカルの声がいい。瑞々しい高音とシャウトが交ざる瞬間の、ギュッてなるところ。エモ好きにはたまらないポイントだ。これはこれで4曲入りのEPとして完成されたものだけれど、まだまだ聴きたい感じがする。早くフル・アルバムを聴かせてほしい。(山本 真由)
-

-
STARBENDERS
Somebody Else
グラム・ロックは音楽性の用語ではなく、華美なファッションを共通項とした70s以来続く振る舞いを指す語である。STARBENDERSの出で立ちはその点でまさしくグラム・ロックだが、シングル『Somebody Else』のパンチも、やはり負けじとグラム・ロックしている。グラム・ロックとも縁深いニュー・ウェイヴやゴシック・ロックから引用した艶やかなシンセサイザーを纏って不敵に闊歩するアンサンブル、そしてその音像を従えていかにもわざとらしくセクシーに歌われるメロディの屈強さが、その何よりの証拠だろう。MÅNESKINやTHE LAST DINNER PARTYのようにあけすけなロック・バンドが脚光を浴びる今日、STARBENDERSが飛躍する条件は十分に整っているのでは。(藤村 太智)
-

-
Taylor Swift
The Life Of A Showgirl
当時最年少でのグラミー賞受賞をはじめ、数々の記録を打ち立て、ヤング・セレブからのビリオネアとなってからも、魂をカントリー・ミュージックに置き、安定したクリエイションとパフォーマンスを続けているTaylor Swift。2025年は、初期音源の権利を自ら買い戻したことでも話題になった。今作では、前作のしっとりとした方向性を残しつつ、シンセ・ポップっぽいノリを抑えて、より大人な魅力を発揮したR&B等、さらに進化したTaylorの歌唱を楽しむことができる。お洒落で恋に生きるギャルな面と、アーティストとしての肝の据わったアティテュードの二面性を持つ彼女らしい、キュートでポップなだけじゃない、スタイリッシュでかっこいいアルバムとなった。(山本 真由)
-

-
WHITE LIES
Night Light
Bruce Springsteenがポストパンクに傾倒し、おまけにダンサブルになったとしたら。そんな荒唐無稽なコラボレーションを、WHITE LIESは最新作『Night Light』でやってのけた。Harry McVeighの歌声は雄々しいワイルドさを獲得し、バンド・アンサンブルの比重が大きく増したことで、作品全体に広がるのはハートランド・ロックのなだらかな風景。この風景は、2025年のUKロック屈指のヒット作であるSam Fenderの『People Watching』にも通ずるものと言えるだろう。そこにシンセサイザーの怪しい眩しさやスクエアなリズム、すなわちポストパンク・リヴァイヴァルの文脈で登場したWHITE LIESの個性が確かに寄り添っている隙のなさもさすがだ。(藤村 太智)
-

-
MAROON 5
The Singles Collection
2025年2月には東京ドーム3公演をソールド・アウトさせ、その人気ぶりを改めて証明したMAROON 5。彼等のキャリアを総括する新たなベスト盤が、日本限定リリースとなった。2015年発表の『Singles』に、近年リリースされたアルバム『Red Pill Blues』(2017年)、『Jordi』(2021年)の収録曲や、デビュー・シングル「Harder To Breathe」等7曲を追加した本作は、まさに最新版にして決定版。全曲がどこかで耳にしたことがあるであろう名曲なだけでなく、ロック×ソウル/R&Bから出発し、EDMやヒップホップ等多様なジャンルを取り入れながら進化してきた歩みは、そのままポップ・ミュージックの近代史を体現しているとも言える。(菅谷 透)
-

-
KULA SHAKER
Wormslayer
前作でオリジナル・メンバーのJay Darlington(Org/Key)が復帰したこともあり、近年これまで以上の創造性を漲らせているKULA SHAKERのニュー・アルバム。ここで感じられるのは、デビューから約30年というベテラン感がいい意味でほとんどない、パワフルで賑やかで彩り豊かなサウンドだ。インド音楽等、東洋的な思想に影響を受けた神秘的な響きと、それをワイルドに再解釈したサイケデリックな表現が、唯一無二のKULA SHAKERの得意分野を前面に出しつつ、且つクラシックなロック・スタイルへのリスペクトも感じられる作品となっている。落ち着いた地位には決して収まらず、自由で知的で茶目っ気もある、KULA SHAKERの魅力を再発見できる。(山本 真由)
-

-
THE LAST DINNER PARTY
From The Pyre
デビュー・アルバムが世界で絶賛された、今最もホットなガールズ・バンド、THE LAST DINNER PARTYの2ndアルバムがこちら。伝統的なUKロックのマナーに則りつつ、野心的で現代的な魅力も持った彼女たち。今作は、挨拶代わりの前作よりも、一歩踏み込んだディープな内容になっている。表現力が足りないと陳腐になってしまいそうなレトロ感、行儀良くなりすぎない程度に滲み出る育ちの良さや、嫌味のない聡明さ、それらが全て絶妙なバランスで成り立ってしまっているのがすごい。ストリングスや管楽器もふんだんに取り入れたリッチなサウンドをバックに、堂々と歌い上げるリード・ヴォーカル Abigail Morrisの年齢に合わない程の貫禄にも驚かされる。(山本 真由)
-

-
THRICE
Horizons/West
スクリーモ・シーンで頭角を現し、次第にオルタナ/アート・ロックへと表現を深化させてきたTHRICE。通算12作目のアルバムは、タイトルが示す通り前オリジナル作『Horizons/East』の延長線上に位置する作品だが、その間に、スクリーモの傑作と名高い3rdアルバム『The Artist In The Ambulance』の再録盤を発表したのも影響してか、近作と比べてもヘヴィな質感が随所で存在感を放っている。ブルージーな歌声と幽玄なサウンドに轟音のテクスチャが溶け込み、前衛的なアプローチも織り込まれた作風は、これまで彼等が探求してきた音楽性の集大成と言うべき、深い衝動を湛えた成熟のロックとして結実。門外漢にも初期のファンにも新鮮に響くはず。(菅谷 透)
-

-
TAME IMPALA
Deadbeat
近年ではプロデューサーとしても存在感を増している、Kevin Parkerが率いるプロジェクトの、5年ぶり5作目となる最新作。これまでサイケデリック・ロック/ポップを軸としたサウンドで人気を博してきたTAME IMPALAだが、本作では、母国オーストラリアのレイヴ・シーンに着想を得たダンス・ミュージックを大胆に展開している。R&Bやディスコからハウス、ビッグ・ビート、EDMに至るまでの系譜を再編成したかのような楽曲群は、自由でいて一貫した美意識が備わっていて、アルバム全体が一晩のパーティーを疑似体験させるような仕上がりだ。ヴォーカルとメロディ、そしてグルーヴに重点を置いたミニマルな音像が、バンド編成のライヴでどう変化するのかも期待したいところ。(菅谷 透)
-

-
MOTION CITY SOUNDTRACK
The Same Old Wasted Wonderful World
2000年代に吹き荒れたエモ/ポップ・パンクの一大旋風も今は昔。さらには、MOTION CITY SOUNDTRACKは長い休止期間を挟んでおり、アルバム・リリースは実に約10年ぶりだ。だからこそ、この『The Same Old Wasted Wonderful World』の若々しさには驚かされた。やはり見逃せないのは、かのPatrick Stump(FALL OUT BOY/Vo/Gt)が参加した「Particle Physics」。シンセサイザーと爽やかなメロディが高揚感を煽る名曲だが、本楽曲に限らずどのナンバーでも徹頭徹尾"あの頃"のワクワクと切なさが聴こえてくるのがなんとも嬉しい。「She Is Afraid」のミュージック・ビデオを見れば明白だが、いぶし銀とは程遠い、ミドル・エイジが青臭くはしゃぐ痛快さが見事な一枚。(藤村 太智)
-

-
TWENTY ONE PILOTS
Breach
母国アメリカでは、スタジアム規模の人気を誇るまでに成長したTWENTY ONE PILOTSが、前作から1年半足らずでリリースした8thアルバム。4thアルバム『Blurryface』から続く壮大なストーリーを締めくくる作品ということで、過去作のオマージュもちりばめられた集大成的な内容になっているが、最も際立つのはジャンルを自在に行き来する実験的で奔放な姿勢だ。エレクトロ・ビートに乗せたラップから、静謐なピアノとヴォーカル、そしてアリーナ・ロックの壮大なコーラスへとシームレスに変化するサウンドには、高揚感と切なく脆い感傷が同居していて、その表現力に圧倒されてしまう。だからこそシーンや年代を問わず多くの人々の心を掴んできたのだろうし、全米1位という結果にも納得がいく。(菅谷 透)
-

-
Ed Sheeran
Play
デビュー作『+』(2011年)に始まり、『-』(2023年)まで5作品にわたって続いた一連の"マスマティックス"シリーズを完結させたEd Sheeranが、ついに新たなフェーズに突入。相変わらずのキャッチーなソングライティングのセンスは健在ながら、今作はより幅広い音楽的要素を取り入れ、ポップ・ミュージックの限界を押し広げたような意欲作だ。彼のルーツの1つでもあるアイルランドのフォーク・ミュージックや、インド、ペルシャ等のエキゾチックで個性的なサウンドも取り入れ、多彩な表現にチャレンジしている。またそういったある種の変わり種に加え、ヒップホップやR&B、ソウルのモダンなスタイルにも手を伸ばし、貪欲なまでの音楽的好奇心に満ち溢れた作品が完成した。(山本 真由)
-

-
ROYEL OTIS
Hickey
"FUJI ROCK FESTIVAL '25"への出演も記憶に新しい、シドニー出身のインディー・ポップ・デュオ ROYEL OTISの2ndアルバム。繊細なヴォーカルとジャングリーなギターで紡ぐ、爽やかな諦観が滲んだスタイルは健在な一方、サウンドは過去作と比較して重厚でリッチなものに。時折顔を覗かせるドリーム・ポップ的な柔らかさには、2人の表現力の躍進が感じられる。タイトなリズムで進行する楽曲はどれも3分前後とコンパクトにまとまっており、次々に身近なメランコリーを切り取るアルバムとしてのテンポの良さは秀逸だ。JOY DIVISIONとネオ・アコースティックを接続した「Car」を筆頭に、インディー・ファンには堪らないささやかな佳作の並んだ一枚。(藤村 太智)
-

-
THE BETHS
Straight Line Was A Lie
2022年の前作『Expert In A Dying Field』が、様々な音楽メディアの年間ベスト・リストに選出され、高い評価を受けた、ニュージーランド出身の4人組 THE BETHS。レーベルをANTI- Recordsに移しての4thアルバムは、前作発表後に起きたElizabeth Stokes(Vo/Gt)の健康問題や、母国での大洪水、家族との関係といった出来事にインスパイアされた、内省的なムードが漂う作品となった。持ち前のキャッチーなパワー・ポップを下地にしつつ、ピアノやオルガン等の楽器も織り交ぜた繊細なサウンドは、円を描くように日々が繰り返す無力感と、そこから立ち上がり前へと歩み出すしなやかさや美しさが感じられる。迷いながらも生きる人々に寄り添い、支えとなる一枚だ。(菅谷 透)
-

-
Alex Warren
You'll Be Alright, Kid (Japan Edition)
SNSを中心に今最もZ世代から支持されるシンガー・ソングライターの1人、Alex Warrenのニュー・アルバム『You'll Be Alright, Kid (Japan Edition)』。彼の歌の何がそんなに人を惹きつけるのか。聴くとホッとするような温かみのある歌声、ドラマチックな楽曲の数々、派手さよりも華やかさよりも実直な音楽。それらを丁寧に紡ぐ、そんな印象だ。幼少期から苦労の多い人生を送ってきたからか、年齢よりも達観しているような安定感がある。そういった面からか、多くの大物アーティストから信頼され、コラボにも引っ張りだこだ。本作では、カントリー・シーンからJelly Roll、K-POPシーンからBLACKPINKのRoséと、ジャンルの垣根を越えた超売れっ子が参加。できすぎでは。(山本 真由)
-

-
PARCELS
Loved
オーストラリア出身で、現在はドイツ ベルリンに拠点を置くバンド PARCELSの3rdアルバム。涼しげなカッティング・ギターと寡黙ながら味わい深い8ビート、グルーヴィなベースで構築されたアンサンブルは、ファンクやAORの古き良きマナーを踏襲した巧みな代物だ。一方で、ソフトなメロディや美しいハーモニー、あるいは曲間で聴こえる談笑が演出する開放的なムードが、聴き手を心地よく脱力させてくれる。快活で小気味よい前半もさることながら、本作では例外的に重心の低い「Everybodyelse」、ミラーボールが揺れるTOTO風のメロウ・ファンク「Summerinlove」、オーセンティックなピアノ・ポップ「Finallyover」と、バラエティ豊かな後半の充実ぶりも見事だ。(藤村 太智)
-

-
SUEDE
Antidepressants
世界的にブリットポップのピュアな魅力が再評価されつつあるなかで、ブリットポップのオリジンとも言えるバンド SUEDEが記念すべき10作目となるアルバム『Antidepressants』をリリース。前作『Autofiction』(2022年)でも錆びない魅力を発揮し、ヒットを飛ばした彼等だが、今回はその前作のプリミティヴなアプローチから、さらに一歩踏み込んだような味わい深い作品となっている。SUEDE流の純粋なギター・ロックと進化した壮大で没入感のあるサウンドは、世相の暗さを反映しつつも、包容力のある温かな音楽で希望を与えてくれる。「Broken Music For Broken People(壊れた人々のための壊れた音楽)」なんて、今まさに人々が必要としているものだろう。(山本 真由)
-

-
Benson Boone
American Heart
ヴァイラル・ヒットをきっかけに、2024年に一躍スターダムを駆け上がったBenson Boone。彼が前作から1年でリリースした最新作『American Heart』は、星条旗を背負うワイルドなアートワークに負けじとパワフルな音楽性だ。1980年代風且つ洗練されたブルーアイド・ソウル・スタイルのトラックを従え、響き渡るヴォーカルには、すでにFreddie Mercury(QUEEN)さながらのヒロイックな風格が感じられる。セクシーなダンス・ナンバー「Mystical Magical」や誠実なバラード「Momma Song」と聴きどころ十分な作品だが、中でも「Take Me Home」から「Young American Heart」で演じられる壮大でノスナルジックなフィナーレは、圧巻のポップ・スターぶり。(藤村 太智)
-

-
HAIM
I Quit
LAのロックな3姉妹、HAIMがニュー・アルバムを引っ提げ、実に12年ぶりに"FUJI ROCK FESTIVAL"に帰ってくる。5年ぶりのフル・アルバムである今作は、抜群のポップ・センスにさらに磨きを掛け、シンプルで牧歌的なアコースティック・ギターの響きと、優しいリズム、姉妹の美しいハーモニーが心に響くコーラス等、野外ライヴでぜひ楽しみたい楽曲が並んでいる。ほろ苦い恋愛をテーマにした歌も、3姉妹にかかれば孤独感や悲壮感はなく、人生の選択を讃える女性のエンパワメント・ソングになる等、彼女たちの活力が感じられる。爽やかなリズムに身を委ね踊るも良し、聴き込んでキャッチーなメロディを一緒に口ずさむも良し、夏の風を感じながらヘビロテしたいアルバムだ。(山本 真由)
-

-
Calum Hood
Order Chaos Order
今やオーストラリアを代表するポップ・ロック・バンドとして世界で活躍する5 SECONDS OF SUMMERの、Calum Hood(Vo/Ba)が満を持してソロ・デビュー。今作『Order Chaos Order』は、バンドとして活動する傍ら、様々なアーティストへの楽曲提供も行ってきた彼らしく、バンドの世界観とは雰囲気を変えたパーソナルな作品となっている。5SOSと言えばボーイズ・バンドというイメージがあるかもしれないが、メンバーはもうアラサー世代。落ち着いた雰囲気のヴォーカルと、ポップだが俗っぽくもないアーティスティックな空気感のサウンドが印象的だ。5SOSのファンはもちろん、インディー・ロックやベッドルーム・ポップをメインに聴いている層にも響く作品。(山本 真由)
-

-
THE INSPECTOR CLUZO
Less Is More
音楽×農業の二刀流で活動する、フランス南西部、ガスコーニュ出身のデュオによる10作目のアルバム。ギター/ヴォーカル&ドラムの最小編成で繰り出される荒々しく豪快なブルース・ロックが話題を呼ぶ彼等だが、わずか4日間で収録されたという本作では、その魅力を見事に凝縮した生々しいサウンドが収められている。エネルギッシュなサウンドで消費社会や愚かさに対して批判する「As Stupid As You Can」、ラウドなサウンドとハイトーンのヴォーカルが印象的な「Less Is More」等、彼等の活動姿勢にも影響を与える思想家のメッセージに触発された楽曲は、実践に基づいた説得力を持っている。彼等がファンを公言するCROSBY, STILLS, NASH & YOUNGの楽曲も聴き応えがある。(菅谷 透)
RELEASE INFO
- 2026.03.10
- 2026.03.11
- 2026.03.13
- 2026.03.14
- 2026.03.17
- 2026.03.18
- 2026.03.20
- 2026.03.21
- 2026.03.23
- 2026.03.24
- 2026.03.25
- 2026.03.27
- 2026.04.01
- 2026.04.03
- 2026.04.06
- 2026.04.08
FREE MAGAZINE

-
Skream! 2026年02月号
Cover Artists
Mori Calliope
























