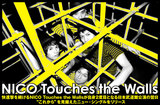Japanese
2019年06月号掲載
NICO Touches the Walls
Member:光村 龍哉(Vo/Gt) 古村 大介(Gt) 坂倉 心悟(Ba) 対馬 祥太郎(Dr)
Interviewer:山口 智男
-対馬さんと一緒に歌詞を書いたのは、なぜだったんですか?
光村:一番の理由は、非常に重たいテーマに取り組みながら、明るい曲調のものもいっぱいあってというときに、僕がまったく明るい気分になれなかったからです(笑)。俺、何ヶ月ぐらい引きこもってたんだろうね? 今年の1月は、対馬君に2、3回会ったくらいで、他の人とはほぼほぼ顔を合わせてないですから。
坂倉:そうだね。去年の12月の中旬ぐらいから。
光村:さすがにこれ以上引きこもっているのは良くないと思って、"歌詞を分担しない?"って対馬君に電話して。対馬君がポップな気分でいるなっていうのは見ていてわかったので、あえて僕の中ではどうしたらいいかわからないポップな曲を渡したんです。
-あぁ、そうなんだ。その中で「サラダノンオイリーガール?」の歌詞は、対馬さんがひとりで書いていますが。
対馬:そうですね。みっちゃん(光村)から電話を貰ったあとに送られてきたのが、その曲だったんです。
光村:"今回のアルバムは自分の中の人生のなぞなぞをテーマにしているんだけど、対馬君の中でこの曲に閉じ込められる疑問はあるか"って伝えてね。そしたら、"どうして女の子はダイエットするんだろう?"って僕が考えもしなかった明るい疑問が返ってきて、"いいと思う。それでいってくれ"って(笑)。
対馬:いや、みっちゃんには深くいってほしいから、俺は浅くいこうと思いながら、他にもいろいろ考えたんですけど、疑問を考え始めたら、自然とこみ上げてくる感情は怒りや不満が多かったんです。それじゃあ、みっちゃんと同じところにいってしまう。それならあえてもっとシンプルなものの方がいいのかなって考えたんです。
-でも、このアルバムの中の救いと言える曲になったと思います。
光村:そう思います。相当暗い気持ちになっていたところに"サラダノンオイリーガール"ってよくわからない単語がきたときに、"俺バカだったな"って(笑)。
古村:あぁ、逆にね(笑)。
光村:肩の力がふっと抜けた感覚はありました。
-歌詞についてもっと聞いてみたい気持ちもあるのですが、ここからは楽曲について聞かせてください。2枚のEPを経て曲作りがさらに自由になったことが窺えるのですが、今回曲作りは楽しかったんじゃないですか?
光村:そうですね。EPを作ってたときにアルバム用に取っておいた曲も半分ぐらいあったから、ほぼほぼEPと同時進行で作っていったんですよ。例えば、「18?」、「サラダノンオイリーガール?」、「MIDNIGHT BLACK HOLE?」はEPを作っている頃にはあって、それらをアルバムに取っておいたぶん、2枚のEPはふっきれた感じになったんですけど、そこでいろいろな実験をした結果、今回はアレンジも構成も徹底的に引き算していって、軸になっている歌が引き立つように作業しましたね。いつもだったら倍ぐらいギターを重ねているところを、ほんとに2本きりでやったり、ドラムもね、『TWISTER -EP-』を作ったとき勉強になったんですけど、シンバルが歌とギターの帯域を邪魔しているからとにかくシンバルを少なくしようってやってみたり。ちなみに、最近の海外の音楽を聴いても、ほとんどシンバルって鳴っていないんですよ。
-そうなんですか。
光村:特に1拍目のクラッシュは、どんなロック・バンドもシンガー・ソングライターも鳴らしていない。それを鳴らすだけでちょっといなたくなるんです。それも含め、シンバルの音数を減らしていって、代わりに声を当てはめるとか、コーラスを当てはめるとかは、"NICO盤"も"ACO盤"も両方で相当意識しました。別の言い方をすれば、世界的に音数が少なくなっていっている――と言ってもレトロなサウンドではなくて、ものすごく洗練された、ある種ヒップホップっぽいというか、サンプリングっぽいものの価値観で音作りしているというトレンドを、自分たちはどう取り入れていくか終始意識して、あまりいろいろな音を重ねないようにしたんですけど、唯一あえて僕らなりにそういうトレンドに逆行したこともあって。最近のトレンドでは、音数が少なくなったぶん一個一個のビートの音が強烈に太くなっているんですけど、それは生音ではなくて、リズム・マシーンを含め、デジタルというか、エレキなものなんですよ。でも、それをその通りにやってもというところで、僕たちはすべて生音でやってみたんです。
-その結果、抜き身のバンド・サウンドと歌詞があいまって、個人的にはNICOの神髄が感じられる作品になったんじゃないかと思いましたが。
光村:自分たちが素の状態というか、素で勝負していくぞっていう感じは、今まで一番強いかもしれないです。その意味では不細工な皺もだいぶ残したというか、どの曲も2テイクぐらいしか録ってないんですよ。
-そのなかで、ギターおよびベースのフレーズや音色はかなり厳選したのでは?
古村:そうですね。音色に関しては、曲にもよるんですけど、レコーディングでは珍しくみっちゃんも僕もほとんどギター1本しか使わなかったです。
坂倉:最初ギターをかなり重ねた曲もあったんですけど、アレンジしながら削ぎ落としていって。
古村:音が少なくなればなるほど、1個気持ちいい音が決まれば、もうそれで全部行けちゃうんですよ。それがうまくハマって、今回は逆に悩まなかったですね。
-「マカロニッ?」をはじめ、"NICO盤"、"ACO盤"共にジャズっぽい要素が随所に散りばめられていますが。
光村:癖みたいなものですね(笑)。そんなふうにいろいろな要素を入れても、歌のテーマはガシっと1本太い筋を通していたので。その筋に枝葉とか苔みたいなものがどうつくかみたいなことも含め、バンドとして楽しんでいるよってことは、『OYSTER -EP-』『TWISTER -EP-』で振りきったことでわかってもらえるんじゃないかと。歌モノに戻っても、"こんな苔がついているよ"みたいに聴いてもらえるんじゃないかと思って。ポップに作ると言うよりは、歌に筋が通っているぶん、そこは謎々のようにあえてアレンジでムフムフしながらやっていたところはありますね。ジャズだけにとどまらず、かなりいろいろなネタは入っていると思うし、ツアーに行った先々で、新曲を聴いた音楽に詳しいイベンターの人たちから、"ありえないミクスチャー"とか、"誰にもわからないギャグだと思うよ"とかって言われます(笑)。
-[NICO Touches the Walls TOUR "MACHIGAISAGASHI '19"]と銘打っているそのツアーは、6月8日のTOKYO DOME CITY HALLと9日の大阪Zepp Osaka Baysideの"-QUIZMASTER-"で終わるわけですが。
光村:そうです。アルバムが出て4日で終わるという(笑)。
-そのあと、アルバムのツアーはやらないのでしょうか?
光村:今のところ考えていないです。今回のアルバムは、個人的な気持ちが充満しているぶんライヴでひとつになるみたいな曲は少ないから、"NICO盤"、"ACO盤"両面のアレンジがあることも含め、ライヴで楽しむというよりも、パッケージとして楽しむ作品としてすごく良くできたと思っているんですよ。だから、ひとりでじっくりと出されたクイズに答えを出すまでのシンキングタイムだと思って、今回のアルバムを聴いてもらえたらいいですね。そういう意味では、次のスタンダードを作りにいったつもりではいるんで、必ずこの先も長く愛せる曲たちになったと思っています。
RELEASE INFO
- 2026.03.14
- 2026.03.17
- 2026.03.18
- 2026.03.20
- 2026.03.21
- 2026.03.23
- 2026.03.24
- 2026.03.25
- 2026.03.27
- 2026.04.01
- 2026.04.02
- 2026.04.03
- 2026.04.06
- 2026.04.08
- 2026.04.10
- 2026.04.15
FREE MAGAZINE

-
Skream! 2026年03月号
Cover Artists
T.N.T