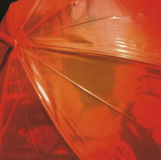Japanese
ReiRay / ハルカトミユキ / yunoka / 中島雄士
Skream! マガジン 2023年10月号掲載
2023.08.04 @下北沢LIVEHOLIC
Writer : 長澤 智典 Photographer:HOSHITO
下北沢にあるライヴハウス 下北沢LIVEHOLICが、8周年記念として行ったイベント"LIVEHOLIC 8th Anniversary series"。8月4日は"LIVEHOLIC 8th Anniversary series~BLOOMAN~"と題し、ハルカトミユキ、中島雄士、ReiRay、yunokaを迎えてイベントを開催。当日の模様をここにお伝えしたい。

 中島雄士のライヴは、シティ・ポップ調のスタイリッシュでお洒落なダンス・ナンバー「噂になっちゃった」からスタート。クリーン・トーンのギターをシャキシャキッと軽快に鳴らし、彼はこの場を身体が揺れるダンス空間に染め上げた。中島雄士の歌声が、いい意味で力の抜けた口当たりの良さを持っているからだろう。歌や演奏に触れていると、心がスーッと曲の世界へ引き寄せられる。
中島雄士のライヴは、シティ・ポップ調のスタイリッシュでお洒落なダンス・ナンバー「噂になっちゃった」からスタート。クリーン・トーンのギターをシャキシャキッと軽快に鳴らし、彼はこの場を身体が揺れるダンス空間に染め上げた。中島雄士の歌声が、いい意味で力の抜けた口当たりの良さを持っているからだろう。歌や演奏に触れていると、心がスーッと曲の世界へ引き寄せられる。
猛暑続く日々のなか、爽やかな夏の風を運ぶように、中島雄士は「高気圧の季節」を歌唱。令和の山下達郎?? と敬称したくなる、爽快さを運ぶポップ・チューンなのが嬉しい。間奏で響かせた歪みを上げたギター・ソロも、楽曲にゲリラ豪雨のような刺激を与えていた。
演奏を止めることなく「最低なドラマ」ヘ。後ノリのビートに歌を乗せながら、中島雄士はこの場に心地よく身体を揺らすドラマを描きだしていった。シンプルな演奏へ、彼の歌声が多種多彩な色や表情を加えてゆく。さりげなく色を重ねながら物語を紡ぐ歌に、気持ちが引き寄せられていた。
途中にTHE BEATLESの「Let It Be」をカバー演奏。ただし、普通にカバーをするのではなく、ループ・マシンを使い、その場で次々と音を重ねたリズム・トラックを作り出す。彼がギターを弾きながら歌うメロディは「Let It Be」だが、リズム・トラックはJohn Mayerの楽曲に仕上げて2曲をマッシュアップ。心地よく跳ねたリズムの上で、同じように「Let It Be」の歌が跳ね続ける。昼下がりに聴きたくなる、小洒落たアレンジも良い。
続く「ODAIBA TOKYO BAY」で中島雄士は、ちょっとチル系の印象も与えるレイドバックなサウンドを奏で、この場にゆったりとした空気を描いた。まったりとした歌の風に触れながら、優しく身体を揺らしていたい。片手にビールがあったら、なおさらこの場の空気にハマるナイス・ミュージックになる。そんなふうにも感じていた。
無機質且つテクノデリックなリズム・トラックが、次第に華やかでソウルフルなダンス・ミュージックへ転化。「Moootion!!!」を通して中島雄士は、この場を夏の野外パーティー空間に塗り替えた。軽やかに跳ねたリズムに身を任せ、クラップをする観客もあちこちに登場。途中から中島雄士はドラムを演奏し、ひとりバンド・スタイルでこの場をハッピーな空気で満たしていった。
最後に奏でた「Awesome Day」でも中島雄士は、ループ・マシンを用いて次々と音を重ねては、フィリー・ソウル/シティ・ポップ&ラップをクロスオーバーした楽曲を作り上げ、素敵な物語を目の前に生み出した。途中からフロアもコーラス隊として加えながら、中島雄士はファンタスティックな空間をこの場に創出。両手を大きく振り上げ楽しむ人たちがフロアのあちこちに生まれていたのも印象的だった。

 続くyunokaのライヴでは、吐息のようなくるみの歌声が、胸に心地よい風を吹かせた。シンプル且つ浮遊感を持った演奏の上で、彼女のヴォーカルが淡い声のグラデージョンを描きだす。「残余」は深い余韻を覚える楽曲で、優しくもダウナーな演奏に身体がゆったりと沈んでいくようだ。でも、まどろむように落ちてゆく感覚が不思議と気持ちいい。
続くyunokaのライヴでは、吐息のようなくるみの歌声が、胸に心地よい風を吹かせた。シンプル且つ浮遊感を持った演奏の上で、彼女のヴォーカルが淡い声のグラデージョンを描きだす。「残余」は深い余韻を覚える楽曲で、優しくもダウナーな演奏に身体がゆったりと沈んでいくようだ。でも、まどろむように落ちてゆく感覚が不思議と気持ちいい。
躍動した熱を一気に注ぐかの如く、yunokaは「バランス」をプレイ。楽曲に力強さが増せば、くるみの歌声にも、凛々しさと身をキュッと引き締める緊張感が漲りだす。曲が進むごとに臨場感を増す演奏。その熱へ誘われるように、観ている側も気持ちの熱を上げてゆく。次第にエモさを増す歌や演奏が心を騒がせる。
クールでスリリングな、でも壮大さを持ったギター・サウンドへ、熱を抱いて躍動するダンス・ビートが重なりだす。yunokaは「三月の憂い」を通し、エモーショナルな熱を気持ちの内側から沸き立てる。抑揚のある演奏に乗せ、心に渦巻く痛い感情を外へ外へと羽ばたかせていた。
「続く晴天」でもyunokaはひとりひとりの感覚を現実から解き放ち、異なる舞台へ導くように、この場に独創的な世界を作った。ギターを下ろし、スタンドに設置したマイクを時折握りながら、くるみは心の奥底から溢れる思いを言葉という祈りに変えて伝えていた。続く「フルムーントーク」では、スタンドから外したマイクを手に舞台の上を左に右へと動きながら歌うくるみに向けて、会場のあちこちでクラップを鳴らす人たちが登場。浮遊感を持ちながらも、身体をこの場から解き放つ熱を抱いたグルーヴが心地よい。「フルムーントーク」を通してyunokaは、この場にいる人たちの身体を優しく揺らし続けていた。曲が進むごとに身体が自由を求めてゆく。
ライヴは「エンドロールが流れる前に」へ突入。いつしか演奏に合わせてゆったりと身体を揺らす人たちが増えていた。yunokaが描き出す、優しくダウナーな、でもエモさを持った歌に気持ちがトリップしてゆく。だから、その身を揺らさずにはいられない。
浮遊感を持ったインスト・ナンバーの「hazy」をブリッジに「空の浴槽」へ。演奏は一気に躍動感を増す。激しい熱を内包した音をこの空間へ次々と解き放つように、yunokaは歌や演奏を届けていた。ひとつひとつの音が強い存在感を持って身体を貫く。気迫に満ちた音の上へ、くるみのエモーショナルな歌声が不思議な彩りを与え、この場を現実から遠ざける。
最後にyunokaは「Signal」を歌唱。先に生まれた熱を抱いた空気の中へ生々しい感情を持った歌を塗り込めながら、3人はこの場にいる人たちの意識を心地よく揺らし続けていた。くるみの歌声が感情的になるほどに心が騒ぐ。じっとなどしていられない。誰もがその場で全身を小刻みに揺らし、舞台の上から放たれるダンス・ロックに身を任せ、胸の内で興奮に酔いしれているように見えた。

 ハルカトミユキのステージは、鍵盤とアコギというシンプルな編成で実施。装飾を拭き取ったからこそ、歌声に込めた思いが、より生々しさを持って胸に突き刺さる。時折ファルセットを交えて届けた「シアノタイプ」に触れながら、ひと言ひと言がチクチクと胸を刺す感覚に強く惹かれていた。色を与えるハルカの歌へ優しく寄り添う、ミユキの美しいコーラスが生み出すコントラストも魅力的だ。
ハルカトミユキのステージは、鍵盤とアコギというシンプルな編成で実施。装飾を拭き取ったからこそ、歌声に込めた思いが、より生々しさを持って胸に突き刺さる。時折ファルセットを交えて届けた「シアノタイプ」に触れながら、ひと言ひと言がチクチクと胸を刺す感覚に強く惹かれていた。色を与えるハルカの歌へ優しく寄り添う、ミユキの美しいコーラスが生み出すコントラストも魅力的だ。
ハルカの歌から始まった「鳴らない電話」では、演奏が始まった途端にフロアからクラップが響きだす。切ない心模様を歌った楽曲なのに温かみを覚えるのは、落ちそうな自分を肯定し、気持ちをしっかり前へと向けようとしていたからか。自分を認めることが、その人の心も強くしていく。ふたりの優しい歌声や演奏に触れながら、切ない心模様をグッと押し上げられる感覚を抱いていた。
MCでハルカトミユキは、下北沢LIVEHOLIC7周年イベントにも参加していたことを語っていた。この箱では常連メンバーのような存在だ。続く「RAINY」では、しっとりとしたエレピの演奏に乗せて切々と言葉を零すように。いや、どこか鈍い色に染まった心模様を歌声の雨に乗せて降らせるようにハルカは歌っていた。モノクロの歌声や演奏に、ふたりは少しずつ色を与えていく。その色をふたりの歌声と演奏を通して覚えるごとに、その思いへ水彩のような淡い色を塗り重ねたくなる。
言葉をゆっくりと紡ぐように歌い奏でたのが「everyday」。思うようにいかないジレンマを消し去ろうともがく思いを胸にハルカは今にも心崩れそうな声をもって、儚い希望に小さな光を注ぐように歌っていた。たとえ変えられない現実が目の前に居座ろうと、そこであがくことで、いつか輝きが降り注ぐ。そんなふうに気持ちをそっと前へ押してくれたのも嬉しかった。
ミユキの奏でるエレピの旋律が跳ねだした。その上へ、力強くストロークをするアコギの音色が重なっていく。スリリングな空気をその場に作りながら奏でたのが「十字路に立つ」、緊張感を与える歌声や演奏だ。いや、切迫した感情を強い意思に塗り替えて吐き出すからこそ、ヒリヒリとした空気が、心地よい緊張感を持った演奏となって届いてきた。ハルカの凛々しい歌声が、たくましい意思を持った言葉としてひとりひとりの心へ突き刺さる。本気で立ち向かう意思を持った言葉が気持ちを熱く揺さぶってくれた。
ふたりの美しいハーモニーから始まったのが「17才」。"17才"という思春期ゆえの焦燥も、大人になって振り返ると、意外とかわいらしいものに見えてくる。それは自分たちが少しは心にたくましい鎧を身につけられたから? あの頃だからこそ感じ、持っていたまっすぐな情熱が、今はとても眩しく見える。それが大人になること? ハルカトミユキが歌い奏でる「17才」に触れながら、10代の頃の自分の姿を思い返していた人たちもいたのではないだろうか。余計な装飾を加えることなく、まっすぐな気持ちのままに歌う姿が、眩しく見えていた。
フロア中から響き渡るクラップもパワーに変えながら、ハルカトミユキは最後に「世界」を力強く歌ってくれた。澄み渡る伸びのある歌声の中に、芯を持った生き様を彼女たちは描き出していた。もがき苦しむことも、何かに抗うことも、絶望に身を浸していようとも、それでも前を向ける勇気を、ハルカトミユキの歌はいつだって与えてくれる。だから観客も熱いクラップをふたりにぶつけながら、舞台の上から溢れ出る希望に満ちた歌の光を少しでも浴びようとしていたのかも知れない。

 この日のReiRayは、エレキとアコギによるアコースティックなスタイルでパフォーマンスを披露した。冒頭を飾った「Skate Girl」から、温かい空気が生まれ始める。観客たちのクラップをドラム変わりに、ふたりは心地よいグルーヴを描くように歌っていた。たとえアコースティックなスタイルに変えようと、スタイリッシュに疾走するエモい感覚はしっかりと生きていた。ふたりがハモリながらドリーミーな夢を描くように歌う声が、嬉しく胸を弾ませる。
この日のReiRayは、エレキとアコギによるアコースティックなスタイルでパフォーマンスを披露した。冒頭を飾った「Skate Girl」から、温かい空気が生まれ始める。観客たちのクラップをドラム変わりに、ふたりは心地よいグルーヴを描くように歌っていた。たとえアコースティックなスタイルに変えようと、スタイリッシュに疾走するエモい感覚はしっかりと生きていた。ふたりがハモリながらドリーミーな夢を描くように歌う声が、嬉しく胸を弾ませる。
忙しない日常に少しの解放感を与えるように、ReiRayは自らの心を少年の頃のような無垢な気持ちに揺り戻し、"夢の続きはどんなだろうね この場所でまた語りあおう"と「Dreaming」を歌っていた。いつまで経ってもあの頃の気持ちを失くすことなく前を見て歩きだそうと彼らは歌う。胸を揺らすふたりのハーモニーに向け、オーディエンスが温かな手拍子を送っていた。
澄みわたる美しくも雄々しいハーモニー。「All About You」でも軽快に走り出した楽曲に気持ちを乗せながら、ふたりは心動くまま高らかに声を上げていた。気持ちへ熱が加わるごとに、ストロークするギターの音にも厚みと迫力が増す。ふたりの沸き立つ感情と演奏がシンクロ。その熱がフロアにも伝播、場内にいる人たちも、いつしか共に歌っていた。
すごくすごく好きだった人のことを思って書いたのは「Precious Moments」。この曲でも、心が動くままにヤジマレイは歌っていた。思いが募るたび、声に熱が膨らみだす。そこには悲しみよりも、大切な人への感謝の気持ちにも似た温かさが満ちていた。だから、ふたりが歌い紡ぐ思いの行く先を見たくて、ずっとその歌声を歌詞に綴った思いを追いかけていた。
観客たちのハンドクラップをリズムに、人の目など気にせず自分らしく生きようという思いを歌ったのが「Pink Hoodie」。軽快に跳ねたスタイリッシュでアーバンなポップ・チューンだ。それをアコースティックなスタイルに変えてさえも、軽やかに疾走するビートが臨場感を持って響いてきた。それこそがReiRayらしいスタイル。ReiRayらしいオンリーワンな姿勢。自分らしさを追求する生き様が、アコースティックな形に姿を変えたことで、より明瞭に伝わってきたのも嬉しい。
台風が過ぎたあと必ず晴れるように、苦しいことの先には必ず明るい未来が待っている。そんな思いを持って作ったのが「Typhoon」。この曲では、それぞれが言葉に熱を強く込め、目の前の陰を吹き飛ばしていく。決して激しく歌うわけではない。むしろ、優しく温かい歌声をふたりは響かせていた。それでも彼らの歌声に熱を覚えるのは、その声に確かな希望を込めて歌っていたからだ。終盤にはふたりと一緒に、フロアも共に声を上げて歌っていた。
最後にReiRayは、セッションを楽しむように観客の声やクラップも混ぜて演奏。ふたりの熱く高ぶる気持ちへ誘われるまま、オーディエンスも「Spotlight」に合わせて身体を揺らし、笑顔を浮かべ、一緒に熱を生み出していった。身体を騒がせ、心を躍らせる。そんなグッド・ヴァイブレーションがこの空間を支配していた。楽しい。その言葉を味わえるライヴをReiRayはしっかりと作り上げていた。
- 1
RELEASE INFO
- 2026.03.04
- 2026.03.06
- 2026.03.10
- 2026.03.11
- 2026.03.13
- 2026.03.17
- 2026.03.18
- 2026.03.20
- 2026.03.21
- 2026.03.24
- 2026.03.25
- 2026.03.27
- 2026.04.01
- 2026.04.03
- 2026.04.08
- 2026.04.10
FREE MAGAZINE

-
Skream! 2026年02月号
Cover Artists
Mori Calliope