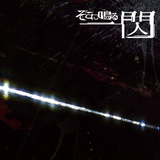Japanese
Suspended 4th
Skream! マガジン 2019年11月号掲載
2019.09.27 @渋谷TSUTAYA O-Crest
Writer 沖 さやこ Photo by ヤスカワ ショウマ
今年7月に、1stミニ・アルバム『GIANTSTAMP』でPIZZA OF DEATH RECORDSから全国デビューしたSuspended 4th。9月に同作のレコ発東名阪ツアーを開催し、ファイナルとなる東京公演にはそこに鳴るをゲストとして招いた。両者の縁は昨年6月、そこに鳴るのツアーの名古屋公演のゲストとして、Suspended 4thが出演したことがきっかけ。音楽性は異なれども、それぞれが目指すミクスチャー・ロックが轟く一夜となった。
 そこに鳴るは全11曲アグレッシヴな楽曲を披露した。濃色のテクニックを盛り込んだ緊迫感のある演奏、ツイン・ヴォーカルが辿るキャッチーなメロディが織りなすコントラストに、観客も固唾を飲みながら熱視線を送る。「6月の戦争」では鈴木重厚(Gt/Vo)と藤原美咲(Ba/Vo)が背中合わせでタッピングなどを披露し、「諦念」は鈴木がハンドマイク・パフォーマンスをするなど、見目的にも華やかなステージを展開。間髪入れず6曲を畳み掛け、MCを挟んでラストまで5曲突っ走るなど、ストイックな姿勢を見せる。「掌で踊る」の滑らかな演奏で場内を華麗に巻き込み、ストレートな歌詞とギター・ロック的なサウンドが強く残る、ラストの「エメラルドグリーン」までエネルギッシュに魅了した。
そこに鳴るは全11曲アグレッシヴな楽曲を披露した。濃色のテクニックを盛り込んだ緊迫感のある演奏、ツイン・ヴォーカルが辿るキャッチーなメロディが織りなすコントラストに、観客も固唾を飲みながら熱視線を送る。「6月の戦争」では鈴木重厚(Gt/Vo)と藤原美咲(Ba/Vo)が背中合わせでタッピングなどを披露し、「諦念」は鈴木がハンドマイク・パフォーマンスをするなど、見目的にも華やかなステージを展開。間髪入れず6曲を畳み掛け、MCを挟んでラストまで5曲突っ走るなど、ストイックな姿勢を見せる。「掌で踊る」の滑らかな演奏で場内を華麗に巻き込み、ストレートな歌詞とギター・ロック的なサウンドが強く残る、ラストの「エメラルドグリーン」までエネルギッシュに魅了した。
 Suspended 4thはセッティング中にKazuki Washiyama(Gt/Vo)が"ちょっと早いんですけど、やっていいっすか?"と言うと、観客から歓声と拍手が。そこからジャム・セッションを経て「GIANTSTAMP」へとなだれ込む。どこか飄々とした空気感を持ちつつも、演奏に迸るのは心地いい緊張感。ハード・ロック、ファンク、ジャズを織り交ぜたサウンドスケープがしなやかに鳴り響く。同じ楽曲でも音源とライヴでは違う印象を与えるバンドも多いが、Suspended 4thは中でもそこに特化した存在だ。楽曲の骨組みを残しつつ、ライヴのたびに違う装いへと変化させていくため、ライヴでしか感じ得ない興奮、この瞬間でなければ生まれないであろうグルーヴやフレーズを次々と投げ込んでくる。まさに文字通り"ライヴ・バンド"である。
Suspended 4thはセッティング中にKazuki Washiyama(Gt/Vo)が"ちょっと早いんですけど、やっていいっすか?"と言うと、観客から歓声と拍手が。そこからジャム・セッションを経て「GIANTSTAMP」へとなだれ込む。どこか飄々とした空気感を持ちつつも、演奏に迸るのは心地いい緊張感。ハード・ロック、ファンク、ジャズを織り交ぜたサウンドスケープがしなやかに鳴り響く。同じ楽曲でも音源とライヴでは違う印象を与えるバンドも多いが、Suspended 4thは中でもそこに特化した存在だ。楽曲の骨組みを残しつつ、ライヴのたびに違う装いへと変化させていくため、ライヴでしか感じ得ない興奮、この瞬間でなければ生まれないであろうグルーヴやフレーズを次々と投げ込んでくる。まさに文字通り"ライヴ・バンド"である。
MCは楽屋のようなナチュラルな空気感。だがWashiyama、Seiya Sawada(Gt)、Dennis Lwabu(Dr)のテンポのいい会話のラリーに、それを無言ながらに豊かな表情で見守るHiromu Fukuda(Ba)という図式にも、4人の心地よいグルーヴが感じられる。ジャズとブラジリアン・ビート感が入り混じる「Vanessa」は甘酸っぱいロマンシチズムが通い、不穏な雰囲気のセクションを中盤に盛り込んだ「ストラトキャスター・シーサイド」は、それを楽しそうに演奏する4人の姿がスリリングに映った。途中"遊びすぎとる? ちょっと真面目にやるわ"とWashiyamaが語り徐々に軌道修正していくが、その"遊び"こそ彼らの核心が露になる瞬間だ。巧みに情景を変えていく手腕はインスト・バンドさながらである。
 開放的な空気感で「ヨンヨンゼロ」を届けたあと、Washiyamaは次に演奏する「think」について触れた。彼が所属する別バンドのメンバーに子供が産まれたことを受けて作ったというが、"どういう視点の曲なのか自分でもよくわかっていなくて、いろんな感情が渦巻いている"と話す。"でも、緊張する空間にはしたくないから、気楽に聴いてもらえたら。地球で一番平和な時間を10分程度お送りします"と告げ、5分以上のインストを経て披露された同曲は、終始深い深い海の中に潜っていくようだった。新しいことが始まっていくような力強さもあれば、エンドロールのように穏やかな終わりも感じさせる。相反する情景や感情がどちらも偽りなく鳴り響く不思議な空間で、その表現が深くなればなるほどに自分がその音と同化していくような感覚に陥った。
開放的な空気感で「ヨンヨンゼロ」を届けたあと、Washiyamaは次に演奏する「think」について触れた。彼が所属する別バンドのメンバーに子供が産まれたことを受けて作ったというが、"どういう視点の曲なのか自分でもよくわかっていなくて、いろんな感情が渦巻いている"と話す。"でも、緊張する空間にはしたくないから、気楽に聴いてもらえたら。地球で一番平和な時間を10分程度お送りします"と告げ、5分以上のインストを経て披露された同曲は、終始深い深い海の中に潜っていくようだった。新しいことが始まっていくような力強さもあれば、エンドロールのように穏やかな終わりも感じさせる。相反する情景や感情がどちらも偽りなく鳴り響く不思議な空間で、その表現が深くなればなるほどに自分がその音と同化していくような感覚に陥った。
本編ラストで「INVERSION」を盛大にぶちかまし、アンコールでは"これがツアー・ファイナルの最後の曲なのか? って感じで終わらそうと思いますが、東京ついてこれる? 俺らの音楽わかってくれ! ストリートの常識がどこまで通用するか見定めてくれよ!"と言い「Betty」を演奏する。ほぼセッション・セクションで構成されたサウンドは、まさにその場の瞬発力や空気感で生まれた濃厚な音像。その繊細で感傷性が高いのに大胆でユーモラスなプレイは、音楽の可能性の極限に挑んでいるようにも思える。15分にわたる演奏の最後にWashiyamaが高らかに叫んだ"次の時代を担うのは俺らだ! ついてこい!"という言葉は、まさにこのツアーを象徴する、そして未来を切り開く決意のひと言だった。

- 1
RELEASE INFO
- 2026.03.04
- 2026.03.06
- 2026.03.10
- 2026.03.11
- 2026.03.13
- 2026.03.17
- 2026.03.18
- 2026.03.20
- 2026.03.21
- 2026.03.24
- 2026.03.25
- 2026.03.27
- 2026.04.01
- 2026.04.03
- 2026.04.08
- 2026.04.10
FREE MAGAZINE

-
Skream! 2026年02月号
Cover Artists
Mori Calliope