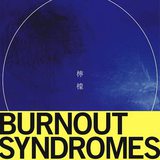Japanese
2019年03月号掲載
BURNOUT SYNDROMES
Member:熊谷 和海(Gt/Vo)
Interviewer:吉羽 さおり
今までで一番ファンの方を向いたアルバムになっている
-そうしたアレンジに加えて、今回は自分でしていたミックスの勉強も役立ち、かなりいろんな知識が生かされた感じですね。
やることが多かったです。エンジニアもアレンジャーもやらなきゃいけなくて。でも楽しいですよね。ひとつを知ると、全然違うところで生かせるんです。ミックスの勉強をしていて、周波数帯に対して造詣が深くなって。例えば「ナミタチヌ」では泡のSEをめっちゃ入れてるんですけど、あのボコボコ、ボコボコっていう音は、単純に景色を作りたくて入れているだけじゃなくて、バスドラの"ボーン"っていう響きの膨らみのところにも泡の音像、泡の音に含まれている低音域を使っているんです。そうやってサウンドの下の部分を支えていたりもしているんですよね。それがないと、すごくスカスカしてるように聞こえるんですよ。これをどうやって埋めようかっていうときに、SEの余波とかで音の隙間を埋めたりとか、リバーブをかけたバスをここにうっすらと入れたりした感じですね。満遍なく同じ帯域にしないと、こういう曲は聴きづらいんですよ。
-リスナーが気持ち良く聴けて、迫力を感じるのは、そういう細部への配慮があるからこそなんですね。
そういうのはエンジニアの勉強をしていて知ったところですね。リファレンスの楽曲とかを聴いていて、"なんでここに変なバスが入ってるんだろう?"っていうのが、なるほどそういうことかっていうのが、だんだんと答え合わせができるようになっていて。それが今回は生きてますね。
-そういったことを知っていく楽しさと、得た知識で自分の音が変わっていく面白さを味わっているというところなんですね。そして、これまでのアルバムでもイントロダクションとなる1曲目は毎回強い引きがありますが、今回の「星の王子さま-Ouverture-」はまさかの翻訳機の音声でスタートするという、意外な始まりですね。
これは、翻訳しているっていうのがちゃんと伝わるかなって考えながら書いていましたね(笑)。歌詞がとにかく難しかったです。なんとなく伝わればいいや、というバンドじゃないので。100パーセント伝えないといけない、そして伝えるためには言わないといけないことがある程度決まっていて。それを限られた文字数でどう並べていくかが大変でした。しかも、メロディでなくセリフのパートなので、伸ばそうと思えばいくらでも伸ばせるんですよね。となると、どこまでが気持ちのいいタイミングでサビにいけるのかとかがすごく難しくて。歌詞はどれもしんどかったですけどね。
-特に、アルバムのブックエンド的な1曲目と最後の曲「星の王子さま-Ouverture-」、「星の王子さま-Fin-」はこの作品の世界観をまとめるうえでの難しさがありそうです。そこでサン=テグジュペリの小説"星の王子さま"というフックを持ってきたことは、いろんな人が入りやすく、ストーリーの流れとしてもリンクしやすい入り口でもあると思います。
アルバムの内容が緻密すぎるので、入り口は何か借りないと、というのはありました。いろんなバランスが繊細なアルバムになっちゃっていて。それが僕にとっては不安な要素でもあったんです。一歩間違えたら崩壊するぞっていう。あとは今回、今までで一番ファンの方を向いたアルバムにもなっているんじゃないかなとも思っていて。この"星の王子さま"の2曲は自分の思いをぶっちゃけた曲だというのもあるし、今回は特にアニメのタイアップ曲があったわけではないので、これを聴いて楽しみにしてくれる人って、本当に僕らのファンだろうなと。そこを意識して書いたというのが一番大きいのかなって思います。
-「星の王子さま-Ouverture-」では、"僕の星には僕しか居ない"、"ようこそ我が星に"というフレーズがあり、ラストの「星の王子さま-Fin-」では"どうだった 我が星は?"と始まって、さらなる仕掛けで展開していく。この"星"にはいろんな意味合いが含まれていると思いますし、これまでこんなふうに自分自身を描くようなことはなかなかしなかったですよね。
"僕が書いてるこの応援歌というのは、実は自分に言い聞かせているだけの詭弁なんだよ"っていうのは、かなりノンフィクションなところなので、それを歌で表現するというのはかなり自分でも勇気がいることで。それで結構吹っ切れたなというのがあります。しかも、この2曲では同じメロディを使っていて、「ラ・マルセイエーズ」(※フランス国歌)のメロディをモチーフにしているんですけど、そういう縛りも作ったので、その限られたなかで顕微鏡を覗きながらピンセットで作り上げるような歌詞作りでしたね。でもこの2曲に関しては、いい感じになったかなと思いました。
-そしてこの2曲のサウンドは、今までのアルバムにもならいつつ壮大な世界観をオーケストラで表現している。
そうですね。でも今までは実際はバンド+ストリングスという感じだったんですけど、今回は一切バンドはなく、オーケストラで。そこはチャレンジでしたね。これもほとんど僕が書いてるんですけど。
-そうなんですか!?
最終的に大嵜慶子さんがアレンジのトリートメントをしてくれているんですけど、構成とか、楽器はほぼ僕が書きました。やっていて楽しかったですね。アコースティック楽器ってすごく音のダイナミクスがつくなと思っていて、打ち込みとはいえ、コントラバスでもめっちゃ小さい音から大きな音まで出るんですよね。それを全部の弦楽器でやったときの気持ち良さというか、クラシックが未だに音楽として愛される理由がよくわかりました。音楽家としてやっていて嬉しいんですよ。めっちゃ楽しい音楽、って思いました。バンドとか電源楽器って、1回弾いたらずっとその音量で鳴っちゃうから、今までの楽曲でもストリングスを入れていたんですけど、それとは全然違う気持ち良さがあって。
-もはやミュージカルや映画を観ているような高揚感がありました。曲の感情やストーリーに合わせるようにして、ブレイクやフィルが入っていって、内省的でありつつ爆発力のあるエンディングとなっている。インタビューの最初の方で語っていた、仕掛け的にひっくり返す場面からの高揚感のある着地は、カタルシスがありますね。
暗いところから明るいところにっていう感じですね。暗いままで終わっても良かったんですけど、やっぱりそれでは気持ち良くはないかなって。1回暗くして、でもやっぱりもう1回ガッと明るくしないとというか。最後にもう1回同じサビ、メロディで展開していくのも気持ちが良かったし。有無を言わさぬかっこ良さみたいのがあるなと思って。
-この頭と終わりの"星の王子さま"2曲があることで、途中の曲、旅はどんなドラマがあっても成立する感覚です。
そうですね。でも、今言ってもらったようなオープニングとエンディングの間にどんな曲がきても成立するっていうのはよくあると思うんですけど。今回はそこもひとつのテーマを持たせていて、色を揃えてあげたいなと思って。実は、間の8曲はいろんな国をテーマにしているんです。「我が家はルーヴル」がフランス、中華っぽい「国士無双役満少女」があり、「あゝ」はスパニッシュっぽいギターがあったり、「ダーウィンに捧ぐ」はアフリカ感があって、「ナミタチヌ」は海の感じであったり、「MASAMUNE」は日本の感じだったりという。それも"星"という意味合いでは、ある種当然の形じゃないですか。なんでもいいように見えて、繋がっていて。サウンドも、その国に合わせて少しずつばらしてあって、そこにもテーマがあるぞっていうことなんです。
-なるほど。そういうところもあったんですね。
なので、結構立体的なアルバムになっているんじゃないかなと思うんです。
-アルバムのタイトル"明星"というのはどのタイミングで出てきた言葉だったんですか。
意味してるところは金星で。金星っていろんな曲のタイトルにもなっていたりして、かっこいい、きれいなイメージというのがあるんじゃないかなって。
-たしかに美しいイメージがありますね。
"ヴィーナス"という言い方もしますからね。でも実際に調べてみると、金星は太陽系で一番危険な星らしいんです。常に硫酸の雨が降り注いでいて、鉄成分の混ざった砂嵐が時速200キロで吹いていて、昼夜の温度差は200度以上みたいな。そういう危険な星らしくて。そういうイメージは全然ないじゃないですか。それがこの"星の王子さま"というストーリーにピッタリと合ってるなと思って。遠くから眺めているだけでは、明星、明けの一番星みたいな、かっこいい感じで言われているけど、実際に足を踏み入れてみると、どろっどろのガスの星なんだよっていうのが、なんかすごく印象的だなって。それでこのタイトルにしようというのは、早めに思っていたんですよね。
-話を聞いて、さらにアルバムを聴いたときにいろんな発見ができそうだなと思いました。今、こういう"アルバム"作りをしている、アルバムの醍醐味を聴かせるバンドも少なくなったなと感じます。
今はバラバラでも聴けてしまいますからね。そこはしょうがないですよね。でもやっぱり"アルバム"の良さってあるじゃないですか。アルバムで出す以上は、ひとつの作品というのがあってもいいのかなと。そこも含めてファンはそういう受け止め方をしてくれると思っているので。そういう人に100パーセント届けばいいなと思いますね。あと今回、最初に思っていたのが、いい漫画とかに出会うと、結末の記憶を消してもう1回読みたいっていうの、あるじゃないですか。そういう作品を作りたいなと思ったんです。聴けば聴くほどやっぱり最初の感動からは薄れてしまって、もう1回記憶を消して聴きたいっていう。そういうものを俺も作りたいなと思ったんです。あの感情をどうやったらアルバムで出せるんだろうって。たぶんそういうのって音楽、特に歌詞の面では難しいと思うんです。それをやりたいなと思って作ったアルバムでしたね。
RELEASE INFO
- 2026.03.04
- 2026.03.06
- 2026.03.10
- 2026.03.11
- 2026.03.13
- 2026.03.17
- 2026.03.18
- 2026.03.20
- 2026.03.21
- 2026.03.24
- 2026.03.25
- 2026.03.27
- 2026.04.01
- 2026.04.03
- 2026.04.08
- 2026.04.10
FREE MAGAZINE

-
Skream! 2026年02月号
Cover Artists
Mori Calliope