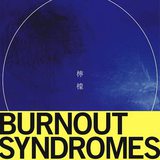Japanese
2016年03月号掲載
BURNOUT SYNDROMES
Member:熊谷 和海(Gt/Vo) 石川 大裕(Ba/Cho) 廣瀬 拓哉(Dr/Cho)
Interviewer:吉羽 さおり
-弾き語りから入ってグラデーション的に曲が色づいていく感じは、考えていたところだったんですか。
熊谷:そうですね。アコースティックな感じではいきたくて。
廣瀬:これは、「FLY HIGH!!」とはまた違うレコーディング・スタジオを使ったんですけど、いい感じで古臭くて枯れた感じも出しながらの音を使って。最後の方は、たくさんスネアだけで重ねたり、フロアタムだけで重ねたりとか、いっぱいやっていて。最後の最後で盛り上がってクライマックスな感じで終われるようにというのはできたかなと。
石川:僕は、2番のAメロの歌詞がすごい好きなんですよ。めっちゃ好きだったので、これはベース入れられへんわってなって、あえてベースを抜いたんですよ。
-歌を聴かせようと、大胆な(笑)。
石川:これはベースよりもハモリやろうと思って(笑)。という感じで、熊谷の歌詞はやっぱり好きなので、それを中心に考えていくとそうなるんです。それで、あんなふうにシンプルな感じにでき上がって。
-これはタイトルにもあるように、後半には「パッヘルベルのカノン」がフィーチャーされていきますよね。この流れは書いたときのアイディアですか?
熊谷:アイディアは最初からありましたね、これがやりたかったんです(笑)。最後に「カノン」に歌詞をつけていきたかったんですよね。それが1番気持ちよくハマるために、「カノン」に向かうまでの3~4分をどうするかっていう課題があったんです。もともと、卒業ソングみたいなものを書きたいなと思ってて。卒業といえば、「パッヘルベルのカノン」かなと。卒業というテーマと昔からある音楽や作品って切り離せないと思うんですよね。卒業を描くときに、そういう要素を無視してオリジナルでやるということが俺にはできないなと思って。音楽が好きな人間としては、卒業といえば「カノン」で。何回も聴いたことがありますしね。そこは避けて通れないような気がしたんですよね。
-卒業時に流れていた「カノン」のイメージってどういうものでした? 悲しみがあるものなのか、逆に華やかな明るさへと向かっていくものなのか。
熊谷:僕自身はやっぱり希望として、捉えてしまいますね。「カノン」を聴くと、卒業式のときの赤いビロードの絨毯があって、パイプ椅子があってという情景が思い浮かびますよね。それを自分なりにどう素材として使うかとなると、最後、みんなで盛り上がっていって湿っぽさをぶっ飛ばすっていう。最終的にはロックなイメージで。だからこそ、今回シングルという小さなアルバムの最後を飾る曲としても相応しいのかなって思って入れたんです。やっぱりクラシックって最後は、ムソルグスキーの「キエフの大門」とかもそうですけど、最後に鐘の音が鳴って、ダーンと終わっていくイメージがあって。そんなものがやりたかったんですよね。
-クラシックはお好きなんですね。
熊谷:そんなに詳しいとは思わないですけど、やっぱりクラシックのフォーマットというか、最後には解放されていくっていうようなフォーマットが自分の中にはあるので。結局そこも避けて通れない気がしていて。そこと、自分ができる楽器と歌っていうのを考えるとこうなるっていう。
-このモチーフを使っての遊び方は面白いと思う。
熊谷:そこも含めて、音楽は自由じゃないといけないのかなって思いますね。完全にオリジナルよりも、こういうやり方の方が伝わるものがあるのかなと。これもまたある種、実験だと思うんです。俺が目指すべきところとしては、そういうところがありますね。コラージュ的な要素って好きなんですよね。
-その着地点が決してアバンギャルドなところでないのが、大事なポイントでもありますよね。
熊谷:どうやって一般的なものとして落とし込むかをいつも悩むんですけど。
廣瀬:うん、たしかにね。
熊谷:それが楽しいところなのかなって。
-そうですよね。メインとなる歌詞を引き立てるためには、ベースを弾かなくてもいいやっていう発想にもなるんですもんね。そういうところも含めて、すごく自由に作っているし、ちゃんと絵やストーリーが浮かび上がるサウンドにもなっている。
熊谷:そういうテレパシーの話だと思うんです。いかにして自分のイメージする映像を明確に伝えられるかっていう。そのひとつの手段として、「カノン」があって。ベースを弾かないっていうことで、ある種の静寂さも出てきますし。結局音楽ってそういうふうに、いかに伝えるかなのかなって、なんとなく見えた気がしているんです。
-そして、誰かの記憶のボタンを押せるような曲になっていくわけですもんね。ちょうど前作『文學少女』のときからこうして取材で話を聞いていると、サウンドもすごくいい変化をしていっているし、今デビューが決まってまた真新しい雰囲気をまとった曲も生まれて。どんどんバンドが広がっていくのもわかりますね。
熊谷:やっぱりレコーディングが大きいと思いますね。すごく貴重な機会だと思うんです。そのたびに、バンドがひと皮剥けたなと感じてもらえればいいなと思うんです。
RELEASE INFO
- 2026.03.11
- 2026.03.13
- 2026.03.14
- 2026.03.17
- 2026.03.18
- 2026.03.20
- 2026.03.21
- 2026.03.23
- 2026.03.24
- 2026.03.25
- 2026.03.27
- 2026.04.01
- 2026.04.03
- 2026.04.06
- 2026.04.08
- 2026.04.10
FREE MAGAZINE

-
Skream! 2026年02月号
Cover Artists
Mori Calliope