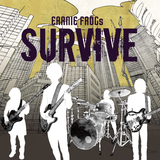Japanese
2019年11月号掲載
EARNIE FROGs
Member:三木 正明(Gt/Vo) おがた(Ba/Vo) テラオ(Gt/Cho) ゆかちん(Dr)
Interviewer:秦 理絵
黄色から橙色へ。アーバンなサウンド・アプローチから、ロックへ。そして、"街に生きる人間"から"人間の心の深いところ"へ。EARNIE FROGsが半年ぶりにリリースするミニ・アルバム『Orange glitter』は、前作『イエロウ・イン・ザ・シティ』と表/裏になるような作品だ。どちらも人の感情の明暗を繊細に歌うという意味では、アーニー(EARNIE FROGs)が結成当初から歌い続けているテーマが貫かれているが、今作からは、様々な葛藤の果てに、それでも自分らしく笑える日々を暮らせたらという生命力が溢れている。以下のテキストでは、そんな今作の制作経緯を訊きつつ、Skream!としてはバンドへのインタビューは6回目ということで、彼らの魅力である男女ツイン・ヴォーカルの在り方と変化についても改めて掘り下げてみた。
-前作『イエロウ・イン・ザ・シティ』(2019年5月リリースの2ndミニ・アルバム)から6ヶ月ぶりっていう、かなりハイスピードなリリースになりましたね。
テラオ:頑張っちゃいました(笑)。
三木:でも、わりと作り溜めてたんですよ。
テラオ:『イエロウ・イン・ザ・シティ』のときに、フルで出すか、ミニ・アルバムで出すかを相談できるぐらい作ってたので、このスパンでリリースできたんです。
三木:「Rock Radio」なんかは『イエロウ・イン・ザ・シティ』のときに録ってましたね。
-今作は、全体的にマイナスの感情も消化して"いろいろあるけど、頑張るしかないか"っていう力強いエネルギーが漂ってるなと思いました。
三木:まさに"Orange glitter"、オレンジの輝きって感じですよね。今回、録り終わったときに、色がオレンジっぽい、人間の意志を感じたんですよ。
テラオ:『イエロウ・イン・ザ・シティ』は"街"がテーマで、全体的に大きな場所にスポットを当てて、そこに住んでる人たちを描くっていうことだったんですけど、今回は、その人たちの中の心に潜る感じがしたんですよね。それで、前作からのカラーシリーズに絡めて、このタイトルになった感じです。
-マクロな視点で"街"を捉える『イエロウ・イン・ザ・シティ』と、ミクロな視点で"人間"にフォーカスをあてる『Orange glitter』が対になるイメージだった?
テラオ:うーん......最初からイメージしたわけじゃなくて、『イエロウ・イン・ザ・シティ』に入らなかった荒くれものたちが『Orange glitter』に入った、に近いかもしれないですね。こいつらだと、"街の統制がとれない!"みたいな曲たちを入れていったら、見事に作品にまとまってくれたんです。だから、結果的に表盤/裏盤ではありますね。
三木:今回は内面系だしね。
テラオ:そう。『イエロウ・イン・ザ・シティ』は大人っぽく自制した感じだったんですけど、『Orange glitter』はエネルギーを発散してるっていう二面性があると思います。
おがた:あと、今回の"オレンジ"には、前回のイエローとは違う意味合いがあって、色自体にメッセージがあると思うんですよ。緑だったら安らぎ、青だったら落ち着きだとしたら、オレンジは躍動感とか生命力を感じる色なので、それに属する曲が集まってますね。
-ゆかちんさんは、今回のアルバムはどんな作品になったと思いますか?
ゆかちん:毎回言ってるかもしれないんですけど、誰も真似できないアルバムになったと思います。"え、こんなことやれるの?"みたいなのが『イエロウ・イン・ザ・シティ』よりも強いし、この荒くれもので1枚の作品としてかたちにできたのは、今まで積んできた私たちの経験があってこそなので、そこはすごく嬉しいですね。
-今作では、今まで以上にアーニーらしさが全開になってますよね。で、その理由はなんなのかっていうのを考えてきたんですけど......。
三木:あははは、我々以上に我々のことを考えてくれてる(笑)。
テラオ:めちゃくちゃ嬉しい。で、その理由は何だと思います?
-最近アップするようになったYouTubeの動画の影響かなって。三木さんとおがたさんのツイン・ヴォーカルを生かした名曲カバー。あれ、すごくいいじゃないですか。
テラオ:ありがとうございます。
三木:ところが、このアルバムはあの動画を始める前に作ってたんですよ(笑)。
-そう、さっき時系列を聞いて、逆だったのかってびっくりしてます。
三木:でも、こういうアルバムを作れる我々だからこそ、今ああいうYouTubeの活動ができるっていうのはありますよね。それこそ『Orange glitter』の原型とかアイディアが3~4年前にあったとしても、今よりチープなものになってた気がするし。
テラオ:ただ、言うならば、「ヴァニラ」とか「Ring Tone」はYouTubeを始めたあとぐらいに録ったんです。だから、もしかしたら、ふたりの声を生かすっていう、あのYouTubeでやってるような手法は、この2曲に強く出てるかもしれないですね。
-なるほど。今思い返すと、初めてアーニーに取材をさせてもらったのが3年前の『リアリティ』(2016年リリースの7thシングル)のときだったんですけど、当時も"ふたりの声が魅力的ですね"っていう話をしたんですよ。三木さんの声が爽やか抜けるのに対して、おがたさんが女性にしては低めのキーを狙えるのが面白いって言ったら、4人とも首をかしげてたんです。
一同:あははははは(笑)!
三木:俺ら、何もわかってなかったね(笑)。
ゆかちん:そのときから気づいてくれてたのに。
三木:でも、当時の反応はたしかにそんな感じだったと思います。
-今は自覚的にふたりの声の魅力を生かせるようになりましたよね。
テラオ:たしかに。昔からこの声を生かしたいなとは思ってたんだけど、自分たちの声の魅力に対して懐疑的だったんですよ。だから、言葉が届かないなっていう葛藤はありつつ、ふたり(三木とおがた)は自分の声が好きじゃないんだろうなとは思ってましたね。
おがた:私は、昔から低い声を評価してくれる人は多いんですけど、バンドのバランスとして、自分が主張するのは求められてないのかなって思い込んでたんです。
テラオ:「MATSURI」(2015年リリースの6thシングル表題曲)のレコーディングをしてたぐらいのときは、両方ともハイトーンで攻めたほうがいいんじゃないかっていう流れもあったしね。
三木:そこから、『ノンフィクション』(2017年リリースの1stフル・アルバム)とか『キャラクター』(2018年リリースの2ndフル・アルバム)っていう作品を作っていくなかで、俺とおがたのいい声に聴こえるキーの高さを生かした曲作りに変わっていったところはありますよね。僕が曲を書いたから僕が歌うとか、おがたが書いたからおがたが歌うっていうことよりも、客観的に見て、どっちがフィットして聴こえるかみたいなやり方に対して、素直に受け入れられるようになった感じです。
おがた:うん。『ノンフィクション』に入ってる「灰色の街」なんかも、私が歌いたかったけど、ちゃんみき(三木)が歌ったほうがいいんじゃないかって判断したし。
テラオ:だから考え方は変わってきてますよね。
おがた:昔は、私はふたりで歌う前提で曲を作ってるけど、ちゃんみきはそういう配分を考えないで作ってるな、とかも気にしてたんですよ。
三木:そんなことないよ(笑)! 俺はそういうのを考えながら作るのが苦手だから、何も考えないで作ったものを、"ここはおがたかな"って振り分けるだけで......。
おがた:それがめちゃめちゃ嫌な言い方をすると、自分はおまけだなって感じてたんです。
テラオ:そんなことないから(笑)。
-おがたさんっぽいですよね。ひとりで考えこんじゃって。
おがた:基本的に卑屈なんですよね(笑)。
テラオ:でも、今は昔みたいに"作った人が歌う"みたいなことに対しても、ふたりにこだわりがあるような感じはしないかも。アーニーが一番良く聴こえる手法をとればいいだけじゃないかっていうスタンスで作ってる気がする。
三木:まぁ、そうだね。
テラオ:それは、たぶん曲作りのなかで、"テラオPポジション"をフルに使わせてもらってるのも大きいんですよ。
-テラオさんが、プロデューサー的な立ち位置で判断していくやり方ですね。
テラオ:そうです。結局、俺から見てると、ふたりの気持ちがわかるんですけど、そこにこだわるのは無益なんですね。
三木:喧嘩みたいになるか、お互いに遠慮し合うかになっちゃうから。
テラオ:ヴォーカリストのこだわりと作曲者のこだわりが別なんだなっていうのは、最近わかったんですよ。やっぱり曲を作ると、深く潜りすぎちゃうんですよね。それがいいものを生み出す原動力ではあるけど、こだわりすぎて人に伝えられない状態で終わっちゃうのが、一番もったいないから。今は三木とおがたが歌ったパターンを聴きくらべて、俺が"この歌はこっち"って言っちゃって、決めている部分が多いですね。バンドの中でバランスをとりにいくのが自分の仕事かなって。それに明確に気づいたのが、前作の『イエロウ・イン・ザ・シティ』とか今回の『Orange glitter』ですね。
三木:今回、「little high」っていう曲でユニゾンしてるんですけど、それもテラオ君の判断のおかげです。
RELEASE INFO
- 2026.03.04
- 2026.03.06
- 2026.03.10
- 2026.03.11
- 2026.03.13
- 2026.03.17
- 2026.03.18
- 2026.03.20
- 2026.03.21
- 2026.03.23
- 2026.03.24
- 2026.03.25
- 2026.03.27
- 2026.04.01
- 2026.04.03
- 2026.04.08
FREE MAGAZINE

-
Skream! 2026年02月号
Cover Artists
Mori Calliope