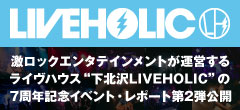Japanese
2025年09月号掲載
PHALUX
Member:一華 ひかり(Vo) Kaichi(Gt) KG(Dr)
Interviewer:サイトウ マサヒロ
-Kaichiさんが大きな影響を受けたアーティストは?
Kaichi:僕は普段あまりバンド系の音楽を聴かなくて。Kawaii Future Bassが好きで、Neko HackerのEDMとロックを融合させるスタイルに影響を受けてますし、kamome sanoさんもよく聴いてます。僕のソロ・プロジェクト(Kaichi Naito)の楽曲に、Neko HackerのSeraさんがギター・ソロで参加してくださったことがあって(2022年リリースの「Starlight Arpeggio (feat. Sera from Neko Hacker)」)、このジャンルで頑張っていこうと思う大きなきっかけになりました。あとはGigaさんとか、EDM系のボカロも好きですね。で、じゃあこのバンドで何ができるんだろうと考えてみたら、かつて親しんでいたラウドロックと最近やってるEDM、そして一華さんがやってきた音楽を掛け合わせることじゃないかと。そこで参考にしているのはCVLTE。最近めちゃくちゃ聴いてますね。
-KGさんはいかがですか?
KG:僕は音楽を始めた頃からずっとヘヴィ・メタルが好きで、最初にハマったのはSLIPKNOTでした。縁の下の力持ちというよりは、最大限に自分らしさを押し出して、限界を突き詰めた結果として表現が広がっているドラマーやバンドが好きだったので、過激なものばかり聴いてました。特にCRYPTOPSYやNILE、FLESHGOD APOCALYPSE。ブラストビートや超高速ツーバスを多用するドラマーには影響を受けましたね。 僕自身はこれまで、GraupelのサポートやovEnolaのメンバーとして、メタルコア・シーンでやらせていただくことが多かったんですけど、このバンドでそのままその表現を取り入れると世界観を壊してしまいかねないので、今は引き算のプレイ・スタイルを目指していて、BRING ME THE HORIZONやARCHITECTSを聴きながら、自身の演奏に還元できないかを考えています。
-いやぁ、本当に三者三様のルーツがあって、面白いメンバーですね。
Kaichi:"音楽性の違い"がすぐに出てきそうな(笑)。
-ちなみに、取材前にいただいた資料には"陰と陽を体現する音楽"というキーワードがありましたが。
一華:これはかなり初期のほうに話していた構想で。ポジティヴな感情とネガティヴな感情のどちらかに寄った曲を作って、ライヴの中でどちらも楽しんでもらえるような演出をしてみたいと思ってたんです。でも正直、現状は"陽"の曲しか作ってない(笑)。ただ、人間誰しも良いところと悪いところを兼ね備えた上での人生だと思うので、それを曲として表現できるようなバンドになりたいですね。
Kaichi:一華さんって、ライヴをめちゃくちゃコンセプチュアルに作り込むんですよ。僕がサポートしたツアーでは火、水、土、風っていう4つのエレメントがテーマになってたり。だから、曲を作る上でもメリハリがあったらいいよねっていう話をしてますね。
-では、記念すべきデビュー曲「PHALUX」について。制作はどのように進んだのでしょうか?
一華:これは、私がソロ時代から一緒に制作している方に要望を伝えて作ってもらったデモを、骨組みとして、Kaichi君がギターやその他のアレンジを加えてくれて、最後に私がメロディと歌詞を付けて完成しました。"パリン"みたいな効果音も入れてくれたよね。
Kaichi:それだけじゃなくていろいろ入れたけどね(笑)。トラック数もかなり多くなりました。基本的に、ドラムとヴォーカル以外のアレンジ周りは全部僕がやらせていただいています。
一華:「PHALUX」がバンドで最初に作った曲だから、探り探りで相当時間がかかったんですけど、その分自分たちのやりたいことに向き合えたから、"これが一曲目に相応しいよね"と言えるものができあがったと思います。
Kaichi:バンドとしての制作フローはまだ定まっていなくて、今はいろいろ試してるんですよ。一華さんのメロから作ることもあれば、先にオケを作ることもあります。
-一華さんの歌のキャッチーさと、プログレッシヴに弾きまくるギター・プレイのコントラストがとても印象的でした。
Kaichi:我々の1曲目として、とにかくやりたいことを詰め込むのがコンセプトだったんですよ。なのでラウドロックの要素が強めになりました。ただ、客層を絞りたくはないので、なるべく幅広い層に届けたいという思いはありつつ......どうしても、ここに全てを注ぎ込むぞっていうギターになってしまいましたね。
KG:僕はこの楽曲の制作途中でバンドに加わったんですけど、当初はキャッチーなポップ・ロックにしたいって話を聞いてたのに、音源は"あれ? 思ったよりメタルじゃない? なんだこれ?"みたいな(笑)。
-結果的に、1発目の楽曲にピッタリなインパクトが生まれましたね。ドラムのアレンジについてはいかがですか?
KG:他のバンドと違うユニークな制作フローで作りました。みんなでDAWの画面を共有しながら、リモートで、リアルタイムでああだこうだと話しながらフレーズを変更していくっていう。なので、ゼロベースで僕が作るっていうよりは2人の要望を受注するような形になったんですけど、それによって面白いアレンジになったんじゃないかと思います。
-ドラムはあえて生音のレコーディングではなく打ち込みにしたそうですね。
KG:はい。もちろん自分で叩きたい気持ちはありつつ、PHALUXでは幅広い楽曲をやっていきたいし、今後Kaichi君が得意としているFuture Bassなどの要素が強まっていく可能性も考えると、アナログな空気感を残すより最初からデジタルなサウンドで作ったほうが、良いものができあがるだろうなと。エンジニアさんからしても加工がしやすくて、納品のスピード感を高められますし。
-なるほど、今後の展開も考えるとそのほうが馴染みが良くなると。
Kaichi:そもそも音源とライヴって全く別物だと思ってて、音源は音源なりの耳馴染みの良さが必要なのかなと思ってます。それに、このバンドはネット音楽とかのリスナーにも聴いてもらいたいと思っているので、ギタリストには嫌う人も多いかもしれないですが、ギターも生っぽくないデジタルな音に寄せてますね。
KG:大サビに入る前のツーバスの連打はライザーっぽく上昇してたりとか、デジタルチックなアプローチをしてますね。
Kaichi:細かく聴くとEDMのビルドアップを取り入れていたり、2Aはわかりやすくトラップ・パートだったりして、そういったビートやエフェクト、シンセの音色と違和感なく展開させるために、バンド・サウンドもデジタルっぽくしようという狙いですね。
-K-POPグループの大規模なライヴに行くと、音源ではハウスだった楽曲がダイナミックにバンド・アレンジされていたりしますよね。
KG:YOASOBIさんもそんな感じですよね。
-あぁ、たしかに。ライヴと音源を別物として捉えるのは、そういったグローバルなポップスの潮流とも対応する考え方かもしれませんね。一華さんは、ソロ時代と比べて、ヴォーカル・スタイルで意識したことはありますか?
一華:自分なりに、バンドの音と自分の声が分離しないような声の出し方を研究しました。今まで通りの歌い方だと、きれいに収まりすぎてしまうというか。なので、その要素を残しつつ、もうちょっとガッツのある、普段より何デシベルかアップしたようなところを狙って歌うことを意識して、レコーディングしました。SNSで毎月楽曲の進捗をピアノ・バージョンで投稿してるんですけど、8月15日にポストした最新の動画は、完全にもともとの私の声で歌ったものなんですよ。なので、楽曲がリリースされたら皆さんに聴き比べてみてほしいですね。
Kaichi:声、全然違うもんね。
RELEASE INFO
- 2026.02.10
- 2026.02.11
- 2026.02.12
- 2026.02.13
- 2026.02.17
- 2026.02.18
- 2026.02.20
- 2026.02.22
- 2026.02.24
- 2026.02.25
- 2026.02.26
- 2026.02.27
- 2026.02.28
- 2026.03.01
- 2026.03.04
- 2026.03.06
FREE MAGAZINE
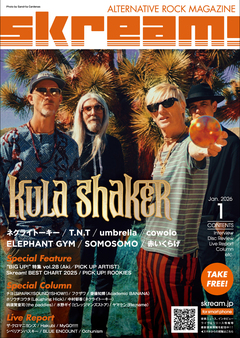
-
Skream! 2026年01月号
Cover Artists
KULA SHAKER