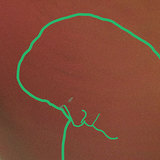Japanese
2020年06月号掲載
Johnnivan
Member:Johnathan(Vo) Shogo(Key) Kento(Ba)
Interviewer:宮﨑 大樹
-"Students"というタイトルは、音楽を常に学んでいきたい姿勢の表れということで。
Johnathan:今回のアルバムで満足しているっていうのはもちろんなんですけど、それと同時にLCD(LCD SOUNDSYSTEM)を超えたいとかそういうことは思ってなくて。その人たちが上にいるっていうのはわかっていた状態で、自分たちのヒーローが出しているものにどう貢献できるか、というか。そういう意味では世界一になろうとは思っていないですし、そこは必要な謙虚さというか、それをタイトルにしたっていう感じです。
-学んで吸収していった先でてっぺんを取りたい、というよりは吸収し続けていきたいというような?
Johnathan:自分の考え方としては、全部吸収しててっぺんに行ったら"もうやめるしかないでしょう"みたいな感じなので(笑)。
-(笑)今回リード曲として「Danced Once」、「Bushwick」の2曲を据えていますよね。
Shogo:10曲のうち、A面は後半に比べたらストレートなアイディアが多くて、B面は各曲違う方面にアイディアを突き詰めているんです。その中で「Danced Once」、「Bushwick」は、A面とB面の各2曲目に入っているんですけど、それぞれの5曲ずつを代表した曲になっているのかなと思います。
-どちらもバンドを知る入り口として相応しい曲だと思います。「Danced Once」はイントロのピアノがクラシック調ですけど、ここはShogoさんがクラシック・ピアノの経験を生かして作り上げていったんですか?
Shogo:デモからピアノはあったんですけど、音色のイメージは変えました。デモのときはもうちょっとスケールが小さいようなピアノの音源だったんです。最初にJohnathanからイメージを聞いたときは、隣の家から聴こえてくるようなピアノの音だったんですけど、曲ができあがっていくにつれて、特にサビとかがある程度大きいスケールの曲になっていきました。それに合わせてピアノをどうしようかなって考えたときに、僕の中では、すごく大きい豪邸の2階の部屋で女の子がピアノを弾いているイメージでプレイしましたね。
Johnathan:仕上がった曲からは全然離れてしまうんですけど、Mitskiの『Be The Cowboy』っていうアルバムの1曲目に「Geyser」っていう曲があるんです。その曲のような、アルバムのオープニング・トラックを想定して書いたんですけど、曲を突き詰めていったら1番、2番、サビ、みたいな感じでスタンダードな構成になっていきました。バンド・メンバーに渡した時点で"これはリード曲でしょう"ってなったので、みんなでレコーディングして、いじくり始めた最初の曲なんです。この曲が決まれば他の曲も上手くいくでしょうっていう予想のもと始めていきました。
Shogo:一番時間がかかりました。各音色のこだわり抜きにかなり時間がかかってますね。
-例えばキーボードではアナログ・シンセが味のある音を鳴らしてますね。
Shogo:単純にアナログ・シンセの音が好きっていうのもあるんですけど、そればっかり入れ込んだらただのマニアになっちゃうので、それを入れるうえで、現代の音楽、Johnnivanの音楽にマッチするためにはどういったアプローチをしたらいいか、アナログ・シンセを使って曲を最大限に生かすっていうのはずっと気をつけています。なので、アナログ・シンセだけを使っているわけではなくて、デジタルのシンセも使ってたり、ソフト・シンセも使ってたり、特に「Danced Once」ではいろいろなシンセをミックスしていますね。ぶつからないように、悪目立ちしすぎないように、アナログ・シンセと楽曲を繋げるために打ち込みのシーケンスを入れたりして、架け橋の部分を上手く入れないと分離しちゃうんですよ。
-Kentoさんは「Danced Once」のベースでどんなことを意識していましたか?
Kento:「Danced Once」のベースはデモのときから一番変わっているかもしれないです。例えばサビでは、他の楽器もビートとか上物とかがガラッと変わったので、それに合わせてベースを聴かせるフレージングにしてますね。サビでいろんなものを追加していったので、ベースの音的には前に出すぎず、埋もれすぎずっていうのを模索しながら作っていった感じです。表舞台には立たないけど、裏のほうでしっかりやっているなっていうのが聴きどころかなと思います。
Shogo:「Danced Once」のベースに関しては、エレクトロニカの要素を入れようかなっていうふうに目指して始まった部分があって。例えばDAFT PUNKのベースとか、前には来ないけど隠れたところで心臓に来るような音が入っていたりして、気づいたら踊りたい気分になる、みたいな。フレーズもそうなんですけど、ちょっとブーストが掛かったような心臓に来る音色みたいなのを目指していきました。
-もうひとつのリード曲「Bushwick」はどんな方向を目指していったんですか?
Johnathan:METRONOMY×KRAFTWERKという方程式ですね。去年の9月くらいになるんですけど、METRONOMYの新作が出て、それに併せて前のアルバムも聴いていたんです。淡々と進んでいくけどぎこちない、みたいな感じがあったので、それをJohnnivanでできないかなと思って作っていきました。
Shogo:これもアナログと曲の融合っていうのを大事にしています。最初のリードとかはアナログ・シンセなんですけど、アコースティックのピアノに上手く繋がるように"ヒュー"っていう風の音で繋げたりとか、ソフト・シンセで繋げたりとか、ほかの楽器も含めての融合感っていうのを大事にしてMETRONOMY感、KRAFTWERK感を追求しました。
Kento:「Bushwick」はベースが引っ張るみたいな感じにはなっているんですけど、一番きつかった曲ではありますね(笑)。というのも、人間が弾いているけどあんまり人間味を出さない、みたいなイメージがありまして。極力人間味を出さず、マシーンになったみたいに淡々と弾いて、でも人間が弾いているっていう絶妙なバランスというか。
-個人的には「Boom Boom」の、だんだん楽器が増えていく感じがアガりました。冒頭には雑音のようなものが入ってますね。
Shogo:曲の雰囲気への導入として使いました。民族音楽的な雰囲気を作りたいなということで、外の雑音から始まっていって、曲が始まったら同じフレーズを叩くドラムが進んでいってジャムっぽくなっていく。曲が終わるころにはまた雑音が入って、"あ、そういえば民族音楽だった"みたいに思う感じで。Johnathan的に曲の書き始めはどんなイメージだった?
Johnathan:TUNE-YARDSの「Water Fountain」っていう曲が一番近い参照元かなと思っています。これはアルバムに入っている曲の中で一番古いもので、このメンバーでバンドを始めてすぐに、アルバムに入っている状態でインストだけはできていたんです。ヴォーカルが思いつかなかったので1年半近く経っていたんですけど、ついにアルバムに入れるぞっていう感じで頑張って考えて。個人的には楽器陣の、カチカチ、ドコドコしている感じの上に、ヴォーカルがふわふわ歌っているという、そのブレンドが成功した部分かなと思っています。この曲、まだバンドでも合わせたことがないんですよ。
-ライヴでどうパフォーマンスしていくのかっていうのはとても楽しみです。曲を制作する段階ではあまりライヴを意識しないという話もありましたけど、Johnnivanのライヴならではの魅力はどんなところにあるんでしょう?
Shogo:音源とはまた違った曲の雰囲気をライヴでは感じてもらえるかなと思っていて。音源でも曲の世界観を突き詰めているんですけど、ライヴは僕らの演奏の特徴というか、演奏から生み出される雰囲気、熱さっていうのをより感じられる、音源とはまた違った世界観を感じられる場所かなって思います。
-ライヴで大切にしていることはどんなことですか?
Shogo:パーフェクトなショーにしたいっていうのはあります。今"熱さ"みたいなことを言いましたけど、エネルギッシュでいい感じならOKではなくて。終わったときに自分たち自身が"今日は最高だったね"ってなるライヴを実現するためにやっているので、それを届けてこそかなと。
Johnathan:基本的な話なんですけど、魅せるカリスマ性だけじゃなく、ちゃんと演奏できているっていうのも揃っていないと、というところですね。
-他の音楽でももちろんそうなんですけど、Johnnivanのライヴではリズム隊がより重要になってきそうですね。
Kento:ビートが崩れると曲そのものの雰囲気も崩れるので、ライヴでは本当に神経を擦り減らせて、ドラムと支えるようなイメージでやっています。あとはオーディエンスの反応を見ながらやるように意識していますね。
-さて、"世界一になろうとは思っていない"という話はありましたが、ではJohnnivanが目指していく先はどこになるのでしょうか?
Shogo:"世界一"は目指してはいないんですけど、アジアのナンバーワンを目指しています。アジアでなんのナンバーワンかっていうと、作品とライヴのクオリティ、これがアジアのナンバーワンであることです。日本のナンバーワンってなると日本向けのナンバーワンになってしまうんですけど、今、アジアのナンバーワンのバンドっていないのかなと思っているので、そういう存在になりたいですね。
RELEASE INFO
- 2026.03.10
- 2026.03.11
- 2026.03.13
- 2026.03.14
- 2026.03.17
- 2026.03.18
- 2026.03.20
- 2026.03.21
- 2026.03.23
- 2026.03.24
- 2026.03.25
- 2026.03.27
- 2026.04.01
- 2026.04.03
- 2026.04.06
- 2026.04.08
FREE MAGAZINE

-
Skream! 2026年02月号
Cover Artists
Mori Calliope